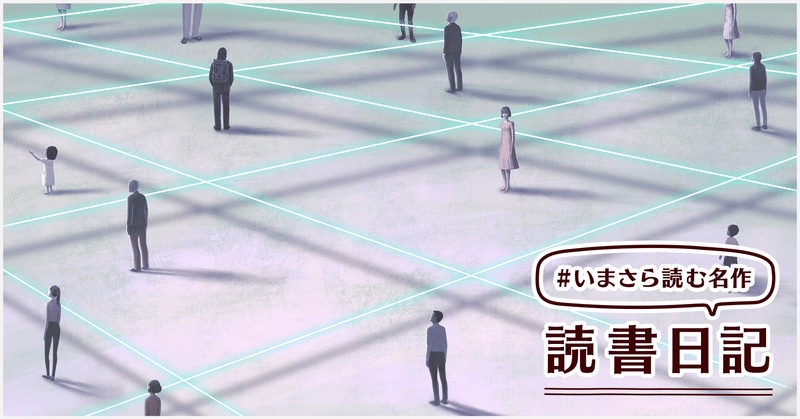
1億冊以上出版された「ミステリーの女王」の代表作|アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』 |monokaki編集部
こんにちは。「monokaki」編集部の碇本です。
今年も残すところ1ヶ月になりました。年末年始には積読している小説をできるだけ読んで過ごすことがこの数年のパターンになっています。新作だけでなく、気になっていた古典なども一緒に読むことが多いです。
年末にはミステリー小説のベスト10などが発表されるので、そこから気になったタイトルを読むという方もいるのではないでしょうか?
ミステリー小説の王道であり、世界中にファンがいる作家であり、多くのミステリー作家に影響を与えたアガサ・クリスティー。彼女の名前や作品名は知っているけど、実は読んだことがないという人もいるのではないでしょうか。
今回はアガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』を取り上げます。
『そして誰もいなくなった』の見事なプロットといったらどうでしょう! 十人の男女が偽の口実でデヴォンの孤島に呼び出され、週末を過ごすことになります。最初の夜、どこからともなく録音の声が流れ、そこに集まった人々全員が過去において殺人を犯したと糾弾し、彼らが殺した”犠牲者”の名まで読み上げます。いずれの場合も、はっきりとした殺人ではなく、目撃者がいなかったために事故や不注意による過失致死、または自殺として片付けられていたというのです。このような”殺人”は通常の場合、白日の下にさらされることはなく、”殺人”とも呼べないものです。しかし、厳密に正義の観点から考えると、トーキィの町の真ん中で白昼堂々他人を射殺するのと、人の命を奪うという点ではなんら変わりありません。ここに本書の道徳的なテーマ――(省略)――があります。
【本文4Pより】
この文章は早川書房から刊行されている『そして誰もいなくなった』(クリスティー文庫)によせられたアガサ・クリスティーの孫にあたるマシュー・プリチャードが書いたものです。
『そして誰もいなくなった』は1億冊以上出版された世界中のミステリ作品でもっとも販売されている作品です。ネタバレもなにもないだろうというぐらいにミステリ作品の古典的な名作であり、日本でも横溝正史、西村京太郎、綾辻行人、米澤穂信などがこのタイトルや内容をオマージュした作品を書いています。
今作ではミステリーの王道ともなっている「クローズ・ドサークル」であったり、「見立て殺人」が使われています。今作を読むとあなたもミステリーが書きたくなるかもしれません。
これ以降、作品ネタバレを含みます。ネタバレされたくない方はお気をつけください。
第1章~第5章
登場人物
ロレンス・ウォーグレイヴ・・・・・・・・・・元判事
ヴェラ・クレイソーン・・・・・・・・・・・・体育教師
フィリップ・ロンバード・・・・・・・・・・・元陸軍大尉
エミリー・ブレント・・・・・・・・・・・・・老婦人
ジョン・マッカーサー・・・・・・・・・・・・退役将軍
エドワード・アームストロング・・・・・・・・医師
アンソニー・マーストン・・・・・・・・・・・青年
ウィリアム・ブロア・・・・・・・・・・・・・元警部
トマス・ロジャーズ・・・・・・・・・・・・・執事
エセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・執事の妻
イギリスのデヴォン州にある兵隊島に招かれた8人とその世話をするために先に島にやってきていた召使の夫婦を合わせた10人がメインの登場人物となります。
兵隊島の主であるオーエン夫妻からの招待状で招かれた(雇われた)彼らでしたが、その招待状自体が虚偽のものであり、彼らは島から出れなくなってしまい、そこで殺人事件が起こっていくという内容になります。
老人はしゃっくりを二回して、沈んだ声を出した。
「嵐が来るな」
「いや、まさか。いい天気だ」
ブロアにそう言われて、老人は気を悪くした。
「嵐が来るんだよ。おれにゃあ、においでわかる」
【本文30Pより】
島に行く前に元漁師の老人との会話の中で島についたあとに嵐がやってきて外部と遮断させられてしまうことが示唆されています。
「腕にスズメバチがとまってますよ。いやーーそのまま、じっとして」ロンバードはもっともらしい手つきで、ヴェラの腕を払った。「ほら、もう大丈夫だ!」
「まあ、助かりました。今年の夏は、スズメバチがとても多いですね」
【本文35Pより】
こちらも冒頭に出てくるシーンのひとつですが、「スズメバチ」というキーワードがのちに起こる殺人事件と結びつきます。ここで読者に無意識に「スズメバチ」という単語が印象づけられています。
前回の太宰治『人間失格』の際にも書きましたが、「チェーホフの銃」というテクニック(概念)と言えるものでしょう。ストーリーに関係するものだからこそ書かれている場面です。それがのちにわかるからこそ効果があります。
ヴェラは暖炉の前に立って、その詩を読んだ。子供の頃から知っている、古い童謡だった。
小さな兵隊さんが十人、ご飯を食べにいったら
一人がのどをつまらせて、残りは九人
小さな兵隊さんが九人、夜ふかししたら
一人が寝ぼうして、残り八人
小さな兵隊さんが八人、デヴォンを旅したら
一人がそこに住むって言って、残りは七人
小さな兵隊さんが七人、まき割りしたら
一人が自分を真っ二つに割って、残りは六人
小さな兵隊さんが六人、ハチの巣をいたずらしたら
一人がハチに刺されて、残りは五人
小さな兵隊さんが五人、法律を志したら
一人が大法官府に入って、残りは四人
小さな兵隊さんが四人、海に出かけたら
一人がくん製のニシンにのまれて、残りは三人
小さな兵隊さんが三人、動物園を歩いたら
一人が大きなクマにだきしめられて、残りは二人
小さな兵隊さんが二人、ひなたに座ったら
一人が焼けこげになって、残りは一人
小さな兵隊さんが一人、あとに残されたら
自分で首をくくって、そして、誰もいなくなった
【本文51-52Pより】
丸いテーブルの中央に、ガラスの丸い台が置いてあり、それに小さな陶器の人形が並べてあった。
「兵隊か」と、アンソニーは言った。「兵隊島だからってことかな」
ヴェラが、前に乗り出した。
「もしかして――いくつあるのかしら。十個?」
「そう、十個ですね」
ヴェラは大きな声で言った。
「あら、おもしろい! これ、童謡に出てくる、十人の小さな兵隊さんじゃありませんか。わたしの部屋のマントルピースの上に、童謡が額に入れてかざってあるんですよ」
「ぼくの部屋にもですよ」と、ロンバードが言った。
「わたしの部屋にも」
「わたしのところにもです」
全員が声をそろえた。
【本文64-65Pより】
少し長い引用ですが、この詩に書かれている内容で兵隊島にやってきた十人は順番に殺されていきます。同時に人形は彼らが殺されていくごとになくなったり壊されていくことで、殺人が行われたことを認知させ、作品に不気味さをもたらしていきます。
すべてが終わると島に呼び寄せられた十人全員が死んでしまう。だからタイトルが『そして誰もいなくなった』ということになるのですが、そうなると真犯人は誰なのか? アガサ・クリスティーはミステリ―的な仕掛けを使って見事に読者を欺いていきます。
「それじゃあ、ちょっとつまらないなあ。出ていく前に、謎を解いたら、どうだろう。まるでミステリ小説みたいじゃないですか。スリル満点だ」
判事が、厳しい声で言った。
「わたしの年になると、そのスリルとやらは、ありがたくもなんともない」
マーストンはニヤニヤ笑って、言った。
「法律一点ばりの生活は、窮屈ですよ! ぼくは、犯罪、大賛成だな。犯罪に、乾杯!」
マーストンはグラスを取って、いっきに飲みほした。
あわてて飲みすぎたのかもしれない。マーストンはむせた。ひどくむせた。苦しそうにゆがめた顔が、紫色に変わった。そして、激しくあえぐと――イスからズルズルとすべり落ち、持っていたグラスが、手から転がり落ちた。
【本文104-105Pより】
スリルとか謎を解こうと最初に言い出す奴たいてい最初に死ぬっていう典型的なパターンですね。
マーストンが死んでしまうとテーブルに置かれていた人形がひとつなくなくなります。ここから連続殺人事件が始まるという合図のようです。また、詩の最初は「小さな兵隊さんが十人、ご飯を食べにいったら 一人がのどをつまらせて、残りは九人」という部分とも彼の死因が呼応しています。そのことにこの時点で気づいたのはヴェラだけでした。
第6章~第9章
「先生、家内です。目を覚ましません。どうやっても、目を覚まさないんです。それに――それに、なんだか、様子がおかしいのです」
アームストロング医師はすばやかった。ガウンにそでを通すと、ロジャーズのあとを追った。
アームストロングは静かに横向きに横たわる執事の妻の上にかがみこんで、冷たい手をとり、まぶたを持ちあげた。二、三分して、彼は身体を起こして、ふりむいた。
ロジャーズが低い声で、ささやくようにきいた。
「家内は――そのう――家内は――?」
乾いた唇をなめている。
アームストロングはうなずいた。
「うむ、亡くなっている」
【本文128-129Pより】
召使のロジャーズ夫妻の妻であるエセルが詩の二番目を彷彿させるように眠りについたまま亡くなってしまいました。
この時点では全体の三分の一ほど進んでいますが、これで二人目の犠牲者が出ました。
「序破急」で考えれば、最初の犠牲者のマーストンが亡くなるまでが「序」であり、「起承転結」で言えば「起」にあたると考えられます。そう、ここからが一気に物語が加速していきます。つまりどんどん殺されていくのです。ミステリー小説を読んでいて読むのが止まらなくなる部分です。ここが面白ければ最後まで誰が犯人なのか気になって、読むのをやめることはなくなる腕の見せ所です。
三人は、島内を一周しだした。
思ったより簡単だった。本土に面した島の北西側は、海から垂直な崖が切りたち、崖の表面はなめらかだった。
島のほかの部分にも樹木は一本もなく、人が隠れられそうな場所はなかった。島の最高部から波打際まで、三人はくまなく丹念に歩きまわった。洞窟の入り口がありそうな岩かげもしっかり調べた。だが、洞窟はどこにもなかった。
最後に波打際沿いに歩いて、マッカーサー将軍が座って海を眺めている場所に来た。寄せる波が岩に当たって砕ける、実に平和でなごやかな景色だ。老将軍は背筋を真っすぐに伸ばして、水平線をじっと見すえて座っていた。
【本文167Pより】
「お嬢さん、事実から目をそらしている場合じゃないでしょう。全員が、重大な危険にさらされている。われわれの中にU・N・オーエンがいる。だが、どの人物がそうなのかはわからない。この島に来た十人の人間のうち三人は、そうではないことは明らかだ。アンソニー・マーストンとロジャーズの妻、それにマッカーサー将軍は言うまでもなく疑惑の圏外に去った。残るは、われわれ七人。この七人の中に、一人だけ偽の小さな兵隊さんがいる、とでも言うかな」
判事は言葉を切って、見まわした。
「わたしの考え方に賛成してもらえるだろうか」
【本文201Pより】
兵隊島にはオーエン夫妻に呼ばれた10人しかおらず、また、本来迎えに来るはずの船もやってきません。食料だけはありますが、彼らはここから出ていくことは現時点では不可能となっています。この作品が出版されたのは1939年でまだ携帯電話などが存在しておらず、外部との連絡を取ることができません。
このように何らかの事情で外界との往来や連絡が断たれた状況、そうした状況下で起こる事件を扱った作品を「クローズド・サークル」と呼びます。
「孤島」「列車」「客船」などバリエーションはいくつかありますが、基本的には密室劇です。また、「クローズド・サークル」ものには特定の人物だけを殺害する場合と全員を殺害する場合のパターンがあり、『そして誰もいなくなった』はタイトルのとおり、全員を殺害するパターンのものです。
2017年に出版された今村昌弘のデビュー作『屍人荘の殺人』が近年では話題となった「クローズド・サークル」もののミステリー小説でした。「このミステリーがすごい!2018年度版」「週刊文春ミステリーベスト10」「2018 本格ミステリ・ベスト10」において第1位を獲得、そして第18回本格ミステリ大賞を受賞し、国内ミステリーランキング4冠を達成するなどその年を代表するミステリー小説になりました。
この作品における「クローズド・サークル」になってしまう「ある特殊な仕掛け」がエンターテインメント性があったことが評価され、さらに普段ミステリーを読まない人にも届いたのではないかと思います。まだ、読んだことのない人は年末に読んでみてはいかがでしょうか?
第10章~第13章
「どうしてときかれても、困るんだなあ。でも、まず、彼は老人だ。そして長い間裁判官をしていた。ということは、ほとんど一年中、万能の神を演じてきたわけだよ。そんなことばかりしていると、いずれは脳みそがふくれあがってしまうにちがいない。自分には万能の力がある、人間の生死をコントロールできると思いこんでしまう。そして、脳みそのどこかがプツッと切れて、もう一歩突っこみたくなることだってある。自ら絶対の審判者にして処刑者になろうと思うわけさ」
「そうねえ、そういうこともあるかもしれないわねえ……」
「あなたは、誰に一票投じますか」
ヴェラはためらわずに答えた。
「アームストロング」
ロンバードは低く口笛を吹いた。
「医者か。ふーん、彼は一番シロに近いと、ぼくは思うけどなあ」
【本文224Pより】
元陸軍大尉のロンバードは元判事のウォーグレイヴが犯人ではないかと話しますが、教師であるヴェラはアームストロングがあやしいと口にします。三人称で書かれている小説ですが、中盤以降はこのふたりがメインのようになって物語が進んでいきます。
ロジャーズは、まもなく見つかった。
裏庭の奥の、小さな洗濯小屋にいた。台所の火をおこそうとして、まきを割っていたのだろう。手にまだ、小さな斧を握っていた。大きいほうの重そうな斧が、ドアに立てかけてある――刃が茶色に汚れていた。その刃と、ロジャーズの後頭部の深い傷が一致することは、明らかだった。
【本文242Pより】
耳の中で、ブーンと音がする――それとも、部屋の中で本当になにかが鳴っているのだろうか。
ミス・ブレントは思った。
“まるでハチが飛んでいるみたいな音ね――ミツバチみたいな”
すぐにハチがいるのが見えた。窓ガラスを這いのぼっている。
ヴェラ・クレイソーンが今朝、ハチのことを話していたっけ。
(中略)
窓ガラスではハチが羽音を立てている――ブーン、ブーン……。
そのとき、チクッとした。
ハチが首の横を刺したのだ……。
【本文260-261Pより】
この前にマッカーサー将軍が散歩から帰らず撲殺死体で見つかっており、召使として島にやってきたロジャーズが四人目、と老婦人のブレントも五人目としてそれぞれが童謡に見立てて殺されてしまいます。残るは半分の五人になりました。
判事が言った。
「今この部屋に五人の人間がいる。五人のうちの一人が人殺しだ。きわめてゆゆしき事態になった。罪のない四人の命を守るために、できうるかぎりの手を尽くさなければならない。それで、アームストロング先生、あんたはどんな薬を持っていますか」
「ここに小さな薬品ケースがあります。調べてくださってかまいませんよ。睡眠薬がいくらか――トリオナールとスルホナールの錠剤です――鎮静剤ブロマイドが一箱、重曹、アスピリン。それだけです。シアン化物はいっさい持っていません」
「わたしも、睡眠薬の錠剤を少し持っている――あれは、スルホナールだと思う。睡眠薬も量が多くなれば、命にかかわる。ロンバードくん、きみはピストルを持っているね」と、判事が言った。
「持っていたら、どうなんですか」フィリップ・ロンバードはキッとなって言いかえした。
「こういうことなんだよ。先生の薬とわたしの睡眠薬、きみのピストル、それにほかの薬品や銃器も集めて、安全なところにしまってはどうだろうか。そのあと一人一人、身体検査と持ち物の検査を受ける」
【本文268-269Pより】
こういう時に理性的な発言をする人間は正しいことをしているように見えますが、同時に何かの意図を持っているのではないかと匂わせてきます。
ウォーグレイヴ判事がどことなく怪しいなと読み進めていくと、
誰かが叫び声を上げた。
ウォーグレイヴ判事は、部屋の奥に置かれた背もたれの高いイスに座っていた。両脇でローソクが燃えている。だが、四人が驚きショックを受けたのは、判事が真っ赤なガウンをまとい、裁判官がかぶるカツラをかぶっていたからだ……。
アームストロング医師がほかの三人に、近づかないように合図した。そして酔っぱらいのような、ちょっとふらつく足で、目を見開いたまま静かに判事に近づいた。
医者はかがみこんで、動かない顔をのぞきこんだ。そしてカツラをひょいと持ち上げた。カツラは床に転がり、禿げあがった額が現れた。額の真ん中が丸く汚れて、そこから何かが滴っている。
アームストロングはグニャリと力の抜けた手をとって脈をみた。そして三人のほうに顔を上げた。
まるで感情のこもらない、ぼんやりとした声で医者は言った。
「撃たれているよ……」
「なんだって――あのピストルか!」と、ブロアが言った。
医者は、やはり気の抜けた声で言った。
「頭を撃ち抜かれている。即死だ」
【本文290-291Pより】
ロンバードが犯人ではないかと推測していたウォーグレイヴの死体が発見されます。ここでも童謡にある詩に見立てられていました。しかし、その詩はすべての部屋に置かれているはずなので、ウォーグレイヴも読んでいたはずです。「小さな兵隊さんが五人、法律を志したら 一人が大法官府に入って、残りは四人」という部分があるので、彼だけが自分の殺される順番を知りえたかもしれない存在だったのに、ここで生存ゲームから脱落します。
残ったのはあと四人。医師のアームストロング、探偵のブロア、元陸軍大尉のロンバード、教師のヴェラです。
十人いた登場人物はそれぞれ個性的でしっかり誰が誰なのかわかりやすいものでした。 このように登場人物が魅力的であることもページを次に進ませる推進力にもなります。「登場人物ってなんですか?」という記事も読んでみてください。きっと、参考になります。
第14章~トロール漁船〈エマ・ジェイン号〉の船長より
「あの童謡のことを忘れているじゃないの。あれに手がかりがあるのに」
ヴェラは、意味ありげな口調で童謡を口ずさんだ。
「“小さな兵隊さんが四人、海に出かけたら、一人がくん製のニシンにのまれて、残りは三人”」
彼女は続けて言った。
「くん製のニシン――これが肝心要の手がかりなのよ。アームストロングは死んではいない……。彼は自分が死んだように見せかけるために、兵隊の人形を減らしたのよ。あなたたちがなんと言おうと勝手だけど――アームストロングはまだこの島にいる。彼の失踪は、くん製のニシンがキツネのにおいを消して、追っている猟犬をまくのとまったく同じなのよ……」
ロンバードがまた腰を下ろした。
「ふむ、きみの言うとおりかもしれないな」
「そうかもしれないが、でもそれなら、やつはどこにいるんだ。捜したんですよ。外も中もすっかり」と、ブロアが言った。
(中略)
ヴェラは声を大きくして言った。
「でも、いいこと、彼は狂っているのよ。なにもかも狂っているのよ! 童謡のとおりに人を殺していくなんて、どう考えたって、まともじゃない! 裁判官みたいなカツラやガウンを着せたり、まき割りをしているロジャーズを殺したり――ロジャーズの奥さんには薬を飲ませて、寝ぼうをさせたし――ブレントさんを殺したときには、ハチまで飛ばしたのよ! まるで子鬼が遊んでいるみたいじゃないの。なにもかも、ぴったりそのとおりだわ」
【本文320-322Pより】
ロンバードが犯人ではないかと言っていたウォーグレイヴの死亡をアームストロングが告げたことにより、彼は自分の予想を撤回することにな りました。そして、ヴェラが犯人では推測していたアームストロングが他の三人の前から消えてしまったことで、彼女は彼が犯人に違いないと残ったふたりに告げます。
「誰かを信じるしかないわ……でも、ブロアのことは、あなたが間違っていると思う。わたしはやはりアームストロングだと思うわ」
ヴェラはだしぬけにロンバードのほうに顔をふり向けた。
「あなた、感じない?――しじゅう誰かがいるような感じ。誰かがこっちをじっと見張って、待ちかまえているような――」
ロンバードはゆっくり言った。
「気のせいなんだよ」
ヴェラはいきおいこんで言った。
「じゃあ、あなたも感じているのね」
(中略)
ブロアが見つかった。東側の石のテラスで大の字になって倒れ、頭を大きな白大理石の固まりで打ち砕かれていた。
【本文328〜331Pより】
ヴェラが感じている視線とはアームストロングがなのか、あるいは他のだれかなのでしょうか? そんな中、生き残っていたブロアが死体で発見されます。
「洋服じゃない―――人間よ……」と、ヴェラが言った。
二つの岩の間に男がはさまれていた。満ち潮で打ち上げられたのだ。
ロンバードとヴェラは、そばまで近づいた。二人はかがんで見た。
紫色に変わった顔――目をそむけたくなるような溺死者の顔……。
ロンバードが言った。
「あっ! アームストロングだ……」
【本文336Pより】
さらにヴェラが疑っていたアームストロングの溺死体も発見され、ついに残されたのはヴェラとロンバードのふたりになりました。どちらが犯人なのか、物語はクライマックスに突入していきます。
ヴェラは反射的に引き金を引いた。
ロンバードの飛びあがった身体が、空中で動きをとめた。そして、地面にドサッと落ちた。
ヴェラはピストルをかまえたまま、そろそろ前に出た。
しかし、用心する必要はなかった。
フィリップ・ロンバードは息たえていた――心臓を撃ち抜かれていた……。
【本文342Pより】
ヴェラはドアを開けた……。
思わず、息をのんだ……。
あれは、なに――天井のフックからぶらさがっているのは――ロープ――しかも、先にちゃんと輪まで作ってある。そして輪に届くように、イスが置いてある――あのイスをければ……。
(中略)
ヴェラはイスの上に上がった。前を見つめる目は夢遊病者の目だった……輪に首を入れた。
ヒューゴーがそこで見守っている――ヴェラがすべきことをするのを――
ヴェラはイスをけった……。
【本文347〜348Pより】
最後に残されたヴェラとロンバードでしたが、10人の中に全員を兵隊島に呼び寄せた犯人がいるというウォーグレイヴの発言に囚われるように、互いに疑心暗鬼になり、行動に起こしてしまいます。
ロンバードを射殺し、錯乱状態になっているヴェラが部屋に帰ると首つり自殺ができる用意がされています。そして、彼女は人を殺めてしまった後悔と混乱によって自ら死を選んでしまうのです。ここで出てくるヒューゴーとはかつての恋人であり、彼女が死なせてしまった子供の叔父にあたります。
ここでタイトルの通り、「そして誰もいなくなった」のです。
しかし、オーエン夫妻を名乗って全員を兵隊島に呼び寄せた真犯人が明かされないまま島での物語は終わってしまいます。
一体ほんとうの犯人は誰なのか。それはこのあとのパートで明かされることになります。
メイン警部は肩をすくめた。
「村人はごく普通の、まじめな船乗りばかりでして。オーエンという人物が島を買い取ったことは知っていました――ただし、知っているのはそれだけでして」
「島の買い取りを仲介したり、必要な手配をしたのは誰なんだ」
「モリスという男です。アイザック・モリスです」
「で、その男は今度のことをなんと言っている」
「なにも言えないのでして、副総監。その男も死にました」
【本文350〜351Pより】
島での出来事が「第16章」で終わると「エピローグ」が始まります。ロンドン警視庁で副警視総監のトマス・レッグ卿とメイン警部がこの事件について物的証拠などから犯人が誰なのか意見を交わしていきます。事件の究明パートに見えるのですが、
「なにをおっしゃりたいのか、わかります。犯人は、ヴェラ・クレイソーンだとおっしゃるのでしょう。クレイソーンがロンバードを撃ち殺し、ピストルを屋敷に持ってかえった。そしてブロアの頭に大理石の時計を落としてから、首吊り自殺を図った。
たしかに筋が通ります――ある点までは。ヴェラ・クレイソーンの部屋にはイスがありまして、それにクレイソーンの靴に付着していたものと同じ海草のついた跡が残っていました。ヴェラ・クレイソーンはそのイスにあがって、ロープを首にかけ、イスをけったように見えます。
ところが、イスはけったままになっていなかったのですよ。ほかのイスと一緒に、壁際にきちんと並べてあった。ヴェラ・クレイソーンが死んだあとに、誰かほかの人間が動かしたのです」
【本文363Pより】
というように彼らは限りなくヴェラが犯人であるという推測を立ててるものの、ヴェラが感じていたように島には彼女をたちを見ていた誰か別の人物が残っていたのではないかと考察します。しかし、彼らにも十人の中の誰が犯人かはわからないのです。
そして、最後の最後に「トロール漁船〈エマ・ジェイン号〉の船長より ロンドン警視庁に送付された証拠文書」という事件の真相を語るパートが始まります。
いわゆる犯人の独白というものですが、ここで真犯人が今回の連続殺人事件の真相(トリックについて)を明かします。このミステリーにおいては事件を解決する探偵も刑事もいないため、犯人自らがトリックなどを明かすことですべてが明らかになるという構成になっています。
私は死刑好きな裁判官と言われている。だが、これはフェアな言い方ではない。私は陪審員に対する事件要点の説示では、常に正しく良心的だった。
感情的な弁護人が感情に訴える弁護をすれば、陪審員は感情に動かされる。それを防いだだけだ。私は陪審員の注意を、証拠そのものに向けさせた。
ところがこの数年、私は自らの変化に気づいた。自分をコントロールする力が弱くなり――人を裁くのではなく、自分で行動したくなった。
正直に言おう――私は自分の手で人を殺したくなったのだ。これは芸術家が自分を表現したくなるのと、まったく変わりない! 私は、犯罪の芸術家だ! 私は犯罪芸術家になれる! 職業ゆえ厳しくおさえられていた私の想像力は、知らず知らずのうちに大きく膨れあがっていた。
私は人を殺さなければならない――どうしても殺さなければならない! さらに、それはただのありきたりの殺人ではいけない。日常茶飯事的な殺人とはまったくちがう、稀有のものでなければならない。その点では、私は少年時代の夢を相変らず持ち続けているのだと思う。
耳目を驚かせるような、不可能なことをやってのけたかった!
人を殺したい……そう、なんとしても、人を殺したい……。
しかし、辻褄が合わないように思えるかもしれないが、生来の正義感が邪魔をした。罪もない人を苦しませてはならない。
【本文367から368Pより】
兵隊島で起きた連続殺人事件の犯人は元判事のウォーグレイヴだったのです。彼は島での6人目の被害者のように見せかけて(アームストロングを脅して協力者にして)死んだ事にして計画を進めていたのです。そして、ヴェラが最後に首をつって死んだのを確認して計画が完遂されたことを見届けてから自殺をしていたのでした。
10人の中でウォーグレイヴが犯人だと睨んでいたのはロンバードだけでした。しかし、ヴェラはそれを信じずにアームストロングが犯人だと思っていた。もし、あの時にロンバードが直感ではなくもっとウォーグレイヴが犯人である理由を述べてヴェラを説得することができたなら、結末は変わっていたのかもしれません。
最後の証拠文書で、島で起きた殺人に関する謎についても犯人が告白することで、トリックが暴かれていきます。完全犯罪になるはずだったものを彼はなぜあえて文書に書き残したのか。それは「何人にも解けない殺人ミステリを案出するのが、私の大きな夢だった」と語り、「自分の頭のよさをほかの人にわからせたいという、いかにも人間的な浅はかな願い」がウォーグレイヴにあったからでした。
世の中にはネタバレを徹底的に嫌う人がいます。確かにネタバレしていないほうが、初めての衝撃を味わうことができます。しかし、ネタバレをしていても楽しめる作品もあります。
『そして誰もいなくなった』はもはや古典ミステリーの代表作のひとつであるので、どういうオチなのかだけを知っている人も多くいるでしょう。私もそうでした。しかし、それがわかっていながら実際に改めて読んでみると作品の構成にも目が行きます。やはり展開の進み具合などがうまくてどんどん引き込まれていきます。そして、犯人であるウォーグレイヴが死んだふりをして周りを欺いているシーンも、普通に読んでいると気づけないような描写や叙述トリックがなされていることに驚きます。
最初にクリスティーの孫であるマシュー・プリチャードが書いた文章で(省略)した箇所がありましたが、そこには「狂信的な法の信奉者が、過去に不正を働いた者を一堂に集め、正義の裁きを下す」という文章が書かれていました。何も知らずに読んだ人でも、ここで犯人がわかるんじゃないかなと勝手に心配してしまいました。
というわけで「いまさら読む名作読書日記」でした。
『そして誰もいなくなった』
著者:アガサ・クリスティー 訳:青木久惠
早川書房(クリスティー文庫)
その孤島に招き寄せられたのは、たがいに面識もない、職業や年齢もさまざまな十人の男女だった。だが、招待主の姿は島にはなく、やがて夕食の席上、彼らの過去の犯罪を暴き立てる謎の声が……そして無気味な童謡の歌詞通りに、彼らが一人ずつ殺されてゆく! 強烈なサスペンスに彩られた最高傑作! 新訳決定版!
「monokaki」は、エブリスタが運営する「物書きのためのメディア」です。

