
おもしろくするためには手段を選びたくない|天祢涼 インタビュー
「一作家一ジャンル」と呼ばれるほど個性的な作家を輩出している「メフィスト賞」を受賞し『キョウカンカク』で2010年にデビュー。2017年に発売になった社会派青春ミステリー『希望が死んだ夜に』では、「おもしろい作家が凄い作家になった」と文芸批評家からも絶賛され、多くの書店員からも支持され店頭でも広く展開された。
そして、精神的な続編ともいえる『あの子の殺人計画』を発表しながら、日常ミステリー『境内ではお静かに』の番外編を小説投稿サイトにも掲載。その幅広い活躍の秘訣を天祢涼氏に聞いた。
自分がいちばん好きなのは小説を書くことだと就活の時に気づく

――小説を書きはじめたきっかけからお聞かせください
天祢:今回取材していただくということで思い出したんですけど、小学2、3年生の頃に『ビックリマン』シールを雑誌なんかで見て、毎回模写してました。たくさんは買えなかったので、自分で妄想してオリジナルシールを描いてたんです。妄想、空想はその頃から好きでした。
――ミステリー自体に興味を持ち始めたり、書き始めたのはいつ頃からですか?
天祢:『ビックリマン』とほぼ同時期にたまたま秋田書店から出ていた子ども用に書き直した『世界の名作推理全集』を読みました。それと出会ったのが大きかったです。『アクロイド殺害事件』にすごく衝撃を受けて、それが原体験でした。
最初に小説を書いたのは小4の時ですね。大河ドラマで中井貴一主演『武田信玄』が好きで、ノベライズを勝手に書き始めて、そこをきっかけに歴史にもハマって読むようになりました。
中2の時にまた自分の中で書きたいブームがきて、夏休みの自由研究で『空上殺人事件』という飛行機の中で殺人事件が起きる話を書きました。これが最初に書いたミステリーだと思います。
――中学時代にはミステリーや歴史なども読んだりもしていたわけですよね。そこから高校・大学とずっと続けて書かれる形になったんでしょうか?
天祢:ほとんど書いた記憶がないですね。大学入試が終わった頃に『スレイヤーズ』が好きだったので、ファンタジーを書いてみたんですが最後まで書けなかったです。
書くのを復活したのは就職活動をし始めたときでした。自分が好きなのが何かなと考えたら小説を書くことだと思って。でも、すぐに小説家になれるものでもなくて卒業後は編プロに入社して、それから7年ぐらいはずっと書いては文学賞に投稿していました。
――2010年にメフィスト賞でデビューされましたが、デビューがミステリーだったこともあってずっとミステリーを書き続けられているのでしょうか?
天祢:ラノベやホラーにも挑戦しましたがうまくいかなくて、すぐミステリー一本に絞りました。やはり最後に謎がポンポンと解けていくミステリーが一番書いていてテンション上がりますね。
当時は短編ミステリーばかり書いていたのですがたまたま復刊した『メフィスト』をブックファースト渋谷店で見つけたんです。最終選考に一度残っただけでそれ以外は一次も通ってなかったので自信喪失して病んでる感じだったんですが、長編を募集しているメフィスト賞を見て、「俺はこれを取るために今まで落ちてたんだ!」と自己暗示をかけまして、いくしかないと。それではじめて書いた長編ミステリーが『キョウカンカク』でした。
「おもしろければOK」だけではなくなった震災後

――デビュー作から読んでいくと出てくる職業のディテールが詳細なのでびっくりしました。作品で書かれる職業や設定などはかなり取材をされて書かれているということでしょうか?
天祢:僕自身が取材をするのが割と好きだからでしょうか。「小説推理新人賞」の最終選考に残った時に編プロを辞めて、ライターをしてました。その時にいろんなところに取材できたんですね。『謎解き広報課』なんかも広報マンを取材するという仕事があって、電話で取材させてもらった方が本当におもしろかったので書くきっかけになりましたね。
――お仕事柄いろんな方からお話を聞く機会があったんですね
天祢:『希望が死んだ夜』や『あの子の殺人計画』は現実の社会問題を取り扱っているので、ある程度リアリティを保たせるためにたくさん取材しました。
『境内ではお静かに』は神社自体は舞台装置で、主人公の青年とかわいい巫女さんをイチャイチャさせたいというそれだけで書いてます。幸いお話を聞かせてもらった神社もそれぞれルールが違ったりして、神社の生活様式とか最低限のもののラインさえ守ったらあとは自由に書いてます。
作品によって、どれだけ取材したものを使うかどうか。リアリティをもたせたいのであれば従うべきですが、そうではなくて書きたいものがあれば舞台装置としては使って、他はこだわる必要はないのかもしれません。
――デビュー作が2010年に出て、翌年には東日本大震災が起きました。執筆に関しての心境の変化などはありましたか?
天祢:まず、小説を書けることが幸せだなと思いました。自分が住んでいる地域は計画停電から外れていて、パソコンを動かせるだけですごいと思ったのがひとつ。
それと、未だにうまく言えないんですが、戦争が終わった時「生き残ってしまった」と思った方々がかなりいらしたらしいんですよね。震災では自分の生活にそこまで大きな影響がでなくて、そういう意味では被災しなかったという後ろめたさのようなものがありました。
そこから単にミステリーで読者をびっくりさせるだけではなく、社会の今を描きたいという気持ちも抱き始めました。かなり時間はかかりましたが形になったのが2017年の『希望が死んだ夜に』です。
――『希望が死んだ夜に』では誰が犯人なのかといよりはなぜその犯行を起こしたのかという「ホワイダニット」に重心が置かれています
天祢:震災の前までは、「ホワイダニット」でも奇抜でおもしろいだけでOKだと思っていた。デビュー作の『キョウカンカク』はその典型です。メフィスト賞はミステリー界の一芸入試と呼ばれていましたから、「そんな理由で人を殺すのっ!?」と単に驚いてほしかった。でも『希望が死んだ夜に』は作品のテーマと絡めた「ホワイダニット」にしたいと思って書きました。
社会派路線とラブコメ路線で精神のバランスを取る

――『希望が死んだ夜に』の続編ともいえる『あの子の殺人計画』を執筆されたいと思ったきっかけなどありましたら教えてください
天祢:『希望が死んだ夜に』を書き始めた頃は、子どもの貧困について話題になり始めた時期で、調べていくとかなり大変なことになっていると思いました。刊行後、「こんな問題があるなんて知らなかった」という反響をたくさんいただいたのですが、子どもの辛さばかりを表に出してしまって、大人の方はうまく伝えられなかった。その反省もあって、貧困家庭の大人を描きつつ、エンタメとして届けるためにはどうするかと考えたことがきっかけです。
――「貧困」がテーマにはあってもミステリー作家として驚かせたいという気持ちがあったんですね
天祢:『あの子の殺人計画』を書いたのは作品の核となるアリバイトリックをひらめいたからなんです。「あっ、このトリックだったらいけるかな」と思ったところからスタートしました。
――『希望が死んだ夜に』は社会派ミステリーですが、『境内ではお静かに』は日常の謎系です。その書き分けなどは意識されていますか?
天祢:ライターをしていたこともあって、編集者から依頼されたものを書くのがプロだというイメージでずっとやっていたけど、それだとどうしても自分の中から振り絞ったものがないなと思ったんですね。
『希望が死んだ夜に』を書いた時には自分の中にあるものをえぐってえぐって書いたような気がした。それからは「このラストシーンが書きたい!」と思えるものだけに書くものを絞るようにしています。そうすると社会派路線か、『境内』のようなラブコメ路線という風になりました。基本的にはその二路線で行きたいです。
――そちらのほうが書き手としてバランスが取りやすいんでしょうか?
天祢:どっちか一本に絞ったほうがいいという人もいます。はっきり言えば、この社会派路線の方が評価は高いんです。しかし、「今回は子どもがネグレクトされたから、次はこれに違う虐待を加えよう」という風に、子どもを不幸な目に遭わせる展開ばかりどんどん求められるのではと危惧してるんです。
そう考えると、ラブコメのようなほんわか路線も書いていった方が自分の精神的なバランスも、書くもののバランスも取れるんじゃないかなと思ってます。
――エブリスタでも掲載されている『境内ではお静かに 小劇場』はどういうきっかけで始まったんでしょうか?
天祢:単純に『境内』のキャラクターをもっと書きたかったんですね。それと、自分の場合はプロットを書くのにすごく時間がかかるんです。そうするとどうしてもプロットと小説の文章は違いますから、小説の勘所が鈍ってきてしまう。番外編はいい意味で複雑なことは考えず、短くパーンと書いて終わりなので、小説執筆のリハビリ的な部分もあったりします。
――「monokaki」はエブリスタのサイトなのでこちらも読んでほしいなと思っています
天祢:実はあまりスターとか見ないようにしてるんです。数値を見るのが好きなので、そっちが気になっていくと凝り性なので本職ではないほうに燃えそうなのが理由です。エブリスタのシステムは、書き手のモチベーションを上げるためにうまくできてますよね。作品の内容としては本編を知らなくても大丈夫ですし、なんにも考えないでたのしく読んでいただければと思います。
おもしろくするためには手段を選ばないことを学んだ

――ご自身の作風に影響を与えたと思われる作家や、他ジャンルの作品がありましたら教えてください
天祢:漫画の『寄生獣』でしょうか。影響を一番受けたのはタイトルのつけ方ですね。「寄生獣」というタイトルの意味がわかるのが物語の終盤、あるキャラクターの一言でそれまでの思い込みが覆され、読んでかなり興奮したのを覚えてます。読み終わった時にこのタイトルはこういう意味だったんだとわかるのがすごく好きです。
あとは『寄生獣』最終巻のあとがきに書いてあったと思うんですが、途中で物語の構想が変わってるんですね。作者が悩んで悩んでラスボスとの決着シーンを変更したと書いてあって、作者が悩んで構想やテーマ性を突き詰めた結果なら変えてもいいんだって教えてもらった気がします。
――タイトルだけではなく、作者の姿勢にもかなり天祢さんは影響を受けてるんですね
天祢:突きつめていくとアメコミの影響も大きいです。アメコミは著作権の問題で同じシリーズでもちょくちょく作者が変わるんです。だから、死んだはずのキャラが「死んだのは偽物だった」とか言って復活したり、ご都合主義なんですけど、いいか悪いかは別にしておもしろくするためには手段を選ばないところがある。
本にする前に直す時間はありますから、よくするために手段を選ばないというのは影響を受けていると思います。『あの子の殺人計画』だと担当編集の荒俣さんに「設定的に宝生視点だと読みづらい」と言われて、前作にも出ていた真壁を出すことになりました。当初、彼は出る予定ではなかった。
――では、『希望が死んだ夜に』の仲田蛍と真壁巧というコンビで考えていた作品ではなかったんですね
天祢:仲田蛍がいれば成り立つものだったんです。だから、ほんとうは宝生と一緒に動いているベテラン刑事がいたんですが、そいつはお払い箱になって幻のキャラクターになりました。『アベンジャーズ』じゃないですけど、真壁の再登場はアメコミとか読んでたからできました。
――これから書きたいと思っている作品、テーマにはどんなものがありますか?
天祢:今は若い人や子どもさんが大変だと思うので、小説を通して彼らの姿を描きつつエンタメとしてもおもしろい社会派路線をやる一方で、ラブコメを極めたい。最終的な目標は極めるとドラマ化とかアニメ化なのかな。
『境内ではお静かに』の久遠雫は「橋本環奈当て書きですよね」とよく言われます。そんなことはないのですが、「環奈ちゃん主演なら大歓迎だな!」とだいそれた妄想をしてます。
あとこの路線というわけではないんですけど、90年代の作品を今の令和向けにリニューアルかリボーンできないかとずっと思ってます。最近自分の中で再ブームになっている『万能文化猫娘』の令和(R)版をやりたいんで、ここは書いといてください(笑)。
プロになれるかなれないかの差は自分にあった書き方が見つけられるかどうか

――デビュー時と現在とでは執筆方法に変化はありますか?
天祢:ブログでも書いたんですが、「青い鳥症候群」的なところがあって、もっと良い書き方があるんじゃないかといろいろ試しています。アプリもデビュー時のものはまったく使ってないです。その結果今に落ち着いています。
プロットを作る際には「Scrivener 3」を使っているのですが、イギリス製のアプリで縦書きが弱い。だから下書きまでした後で、物書堂の「egword universal 2」を使って縦書きで清書して担当さんに送っています。
それ以外だと登場人物の設定を細かく決めるようになりました。デビューの頃は名前と一言プロフィールぐらいしかなかったんですが、それだと書き進めていくうちにブレてしまう。書いているうちにこういう人だとわかってくるブレならいいんですが、芯がないとあっちに行ったりこっちに行ったりと整合性が取れなくなってしまう。
――キャラクター小説であったり、バディものだとそれぞれのキャラがたっていないと進めづらいですよね
天祢:そうですね。書きながら考えた方がキャラクターが動いていいと聞いて、それもやっていたのですが、自分の場合は伏線が多いミステリーが主戦場なのでどうしても辻褄が合わなくなってしまう。だからプロット段階で細かく考えてます。フォントの色を変えてハートマークをつけて「このキャラクターはこう思ったからこう言っている」みたいなことも書いている。
ここまで設定してもブレることはあるのですが、基本は固めてあるので「もっといいものを思いついたからブレたんだ」と前向きに考えられるようになってきました。
――最後に、プロをめざす書き手に向けてのメッセージがあればお願いします
天祢:精神論と技術論の二つがあるんですがまずは精神論から。
デビューしてもなかなか売れないこともあるし、評価されないこともあるし、版元との関係性もあります。僕は3作目ぐらいの時に全然売れなくて、原書房さんに拾ってもらったんですが、拾ってもらっても書くのが好きじゃないと書けなかったと思います。書くのが病的に好きな人じゃないとプロになってからは難しいのかもしれません。
技術論で行くと小説を読むのが好きで、書くのが好きだったら誰でも小説家になれる素養があるはずです。それでプロになれるかなれないかの差は自分にあった書き方を見つけられるかどうかだと思います。
例えば、「その人になり切って質問に答える」という登場人物の作り方があります。ある編集さんはそんなことをしても意味がないと切り捨てているけど、すごく売れている作家さんはそれをやって実際に成功している。
結局、どのやりかたが正しいのかという正解がない。色んな人が色んな書き方について言っていると思いますが、その中で自分に合ったものを見つける。それができればプロになれるかもしれない。
――そのためにはいろんなものを試さないといけないし、知らないといけませんね
天祢:もしプロになりたいけどなれないでくすぶっているのであれば、とりあえず好きな作家さんの書き方を調べてみる。真似してみて合わなかったらまた違うやりかたを見つけて真似してみる。それを繰り返していくと自分に合ったやり方が見つかるかもしれない。書き方はほんとうに正解はないと思う。答えがないというのが答えなんです。
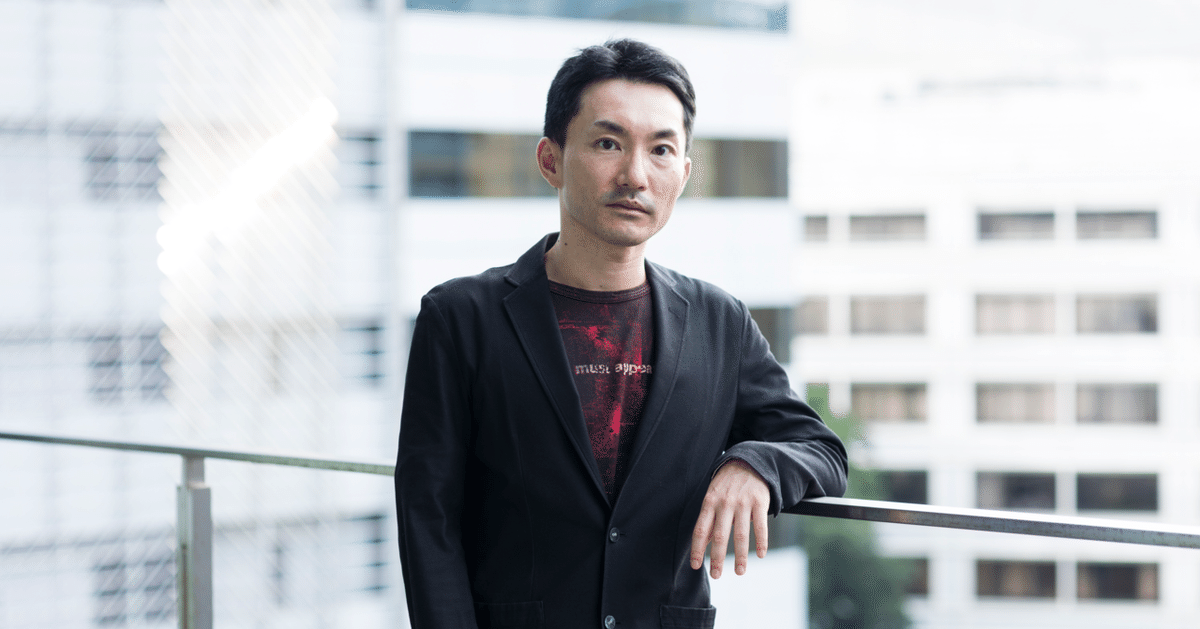
(インタビュー・構成:monokaki編集部、写真:鈴木智哉)
『希望が死んだ夜に』
写真:青山裕基
装丁:永井翔
神奈川県川崎市で、14歳の女子中学生・冬野ネガが、同級生の春日井のぞみを殺害した容疑で逮捕された。少女は犯行を認めたが、その動機は一切語らない。何故、のぞみは殺されたのか? 二人の刑事が捜査を開始すると、意外な事実が浮かび上がって――。現代社会が抱える闇を描いた、社会派青春ミステリー。
『あの子の殺人計画』
写真:青山裕基
装丁:関口聖司
椎名きさらは小学五年生。母子家庭で窮乏している上に親から〈水責めの刑〉で厳しく躾けられていた。ある時、保健室の遊馬先生や転校生の翔太らに指摘され、自分が虐待されているのではないかと気づき始める……。
一方、JR川崎駅近くの路上で、大手風俗店のオーナー・遠山が刺し殺された。県警本部捜査一課の真壁は所轄の捜査員・宝生と組んで聞き込みに当たり、かつて遠山の店で働いていた椎名綺羅に疑念を抱く。


