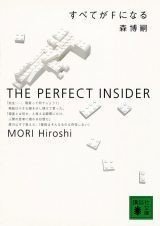「キャラクター小説」というイノベーション|京極夏彦と森博嗣|仲俣暁生
ある作家の登場以前と以後とで、小説のあり方が完全に塗り替えられてしまうような出来事は、そうそう何度も起きるものではない。いかに素晴らしい新人でも、先行する作家や作品の延長線上に位置づけられることのほうが多いからだ。
だが平成6年に登場した一人の新人小説家に関しては、そのような先行例を見出すことが難しい。京極夏彦のことである。
そのデビュー作『姑獲鳥の夏』を書いたとき、京極夏彦は現役のデザイナーだった。しかもこの作品は新人賞に応募されたのではなく、いわゆる「持ち込み」(編集部への一方的な投稿)だった。通常そのような「持ち込み」原稿は、いったん既存の新人賞の審査にまわされることが多い。京極の作品を受け取った講談社には、昭和30年に創設された伝統あるミステリ賞として江戸川乱歩賞がある(前年は連載第3回で紹介した桐野夏生の『顔に降りかかる雨』が受賞)。京極の作品もこの選考にかけられておかしくなかった。
だが『姑獲鳥の夏』はその完成度の高さゆえ、ただちに出版が決定した。そして、ほとんど先行例のない魅力を湛えたこの作品は読者に――そして同時代のミステリ作家たちにさえ――大いなる衝撃と共感をもって受け止められたのだった。
それだけではない。京極夏彦の登場は平成8年の雑誌「メフィスト」創刊と「メフィスト賞」の設立、さらには雑誌「ファウスト」の創刊へとつながる、平成ミステリ史の大きな流れを生むことになったのである。
グラフィカルなタペストリーとしての「小説」
それほどの衝撃を多くの者に与えた『姑獲鳥の夏』とは、どのような話か。
物語の舞台は第二次世界大戦が日本の敗北で終わり、進駐軍による長期占領が終わって間もない昭和27年夏の東京である。不思議なことに、日本が占領下にあったことは作中で明瞭に描かれず、むしろ戦前や戦中との精神的な連続性が強調されている。
「私」という一人称で語り手役を演じるのは、関口巽という新進小説家である。この人物がある夏の日、「どこまでもだらだらといい加減な傾斜で続いている」坂道を歩いているところから、この物語は始まる。彼がめざすのは「京極堂」という古本屋だ。
京極堂の主人、中禅寺秋彦(作中では「京極堂」と呼ばれるので、ここでも以下それに倣う)は関口の旧制高校時代の同級生で、陰陽道の流れを汲む神主の一族でもある。関口は京極堂に「二十箇月もの間子供を身籠っていることができると思うかい?」と尋ねる。
この問いに対して京極堂が答える次の言葉は、この小説から始まる「百鬼夜行」シリーズを貫く通奏低音となる。
「この世には不思議なことなどなにもないのだよ、関口くん」
これ以後、ペダントリー(衒学趣味)に満ちた京極堂の長広舌を関口は――そして読者もまた――延々と聞かされることになる。京極堂は関口の問い一つから、多くの真実を言い当ててしまう。かくして、京極堂がホームズ、関口がワトソンの役をそれぞれ演じるかたちで物語が展開しはじめるのだ。
しかし、それだけのことであれば、『姑獲鳥の夏』があれほどまでの衝撃を与えることはなかっただろう。この小説には二人目の「探偵役」として、榎木津礼二郎という旧華族の御曹司が登場する。彼は本職の私立探偵であり、京極堂や関口とは旧制高校の一年先輩にあたる。さらに榎木津の幼馴染みである麻布署刑事課の巡査・木場修太郎が、作中で展開する奇妙な事件の捜査の主体となる。
京極堂・榎木津・木場がそれぞれ強烈な個性の持ち主であるのに対し、語り手の「私」は過去に鬱病に苦しんだこともある、きわめて内省的な人物だ。関口はワトソン的な語り部であるだけでなく、これら奇矯な人物たちの「いじられ役」を作中で演じることになる。そう、『姑獲鳥の夏』は内省的な語り手=「私」による文学作品にみせかけた、いまでいう「キャラクター小説」だったのだ。
言い換えるならば、京極の作品は(その後にシリーズされる)各作品の題名に掲げられた「妖怪」を観念の中心に据え、その周囲にこれらの登場人物を巧みに配置した、曼荼羅やタペストリーのようなグラフィカルな構築物とでも言うべきものだった。
「私」もまたキャラクターにすぎない
京極夏彦は、翌年の平成7年に発表された第2作『魍魎の匣』でブレイクする。日本推理作家協会賞(長編部門)を受賞したこの作品では、関口巽が「私」として一人称で語るだけではなく、三人称による描写が導入された(第3作『狂骨の夢』では関口による一人称は消滅する)。かくして純粋なキャラクター小説としての自由を獲得したこのシリーズは、一作ごとに長大となり、文庫版で軽く1000ページを超えるようになっていく。
個人的には、関口が一人称で語る『姑獲鳥の夏』がもっとも印象的な作品でありつづけている。それは同作が純粋な「キャラクター小説」と一般的な文芸作品との中間形態だからかもしれないし、純文学における「私」でさえ、「そうした役割を演じさせられるキャラクター」にすぎないことを、あからさまにしてしまった作品だからかもしれない。
京極のその後の活躍については、言葉を費やすまでもない。平成9年には『嗤う伊右衛門』で幻想文学的な作品に与えられる泉鏡花賞を受賞、平成15年には『後巷説百物語』で直木三十五賞も受賞し、小説界の重鎮としての座を占めることになった。しかし京極夏彦の書く「小説」は、やはり一般的な文学作品とはどこか、根本的に手触りが違う。言語表現というよりは「文字表現」であり、あくまでもグラフィカルなものだ。
「文学」の世界で高く評価されるようになっても、京極夏彦は「キャラクター小説」の倫理に忠実であり続けている。デビュー作以来書き続けてきた「百鬼夜行」シリーズの世界観と設置をfounderとして解放し、他の書き手による新作の創造を認めるシェアード・ワールドシリーズとして平成27年に「薔薇十字社叢書」というプロジェクトを始めた。薔薇十字社叢書からは佐々木禎子『座敷童の誕』をはじめ7作が生まれ、平成29年には第二期として佐々木禎子、愁堂れな、和智正喜による3作が追加されている。
文芸というジャンルのイノベーションをめざした「メフィスト賞」
ところで京極夏彦の登場は、想定外の大きな副産物を生んだ。冒頭に話題にした公募新人賞「メフィスト賞」の創設である。
メフィスト賞の特徴はただ一つ、下読み選考を行わず、雑誌『メフィスト』の編集者自身が、すべての投稿原稿を読んだ上で選考を行うことだった。その狙いは、既存の新人賞(たとえば自社が開催する江戸川乱歩賞)に応募するようなタイプの新人とは異なる、文芸というジャンルのルールを更新(イノベーション)してくれるような才能を求めることだった。そうした期待に応えるかのように、メフィスト賞には文字どおりに「型破り」な書き手たちが集まった。平成9年に『すべてがFになる』で栄えある第1回メフィスト賞の受賞者となった森博嗣を、その筆頭に挙げるべきだろう。
森博嗣はデビュー作『すべてがFになる』が発表された当時、名古屋大学の現役の助教授だった。森がメフィスト賞に応募したのは『冷たい密室と博士たち』という作品(のちに第2作として刊行される)だったが、編集部からの要望を受け、同じキャラクターが登場するシリーズ作をデビュー前に何本も書き下ろしていた。『すべてがFになる』は書かれた順番でいうと4作目にあたる。つまり森博嗣はデビュー時に、すでにストック作品がほかに3作もある状態だったのだ。
『すべてがFになる』の登場も、京極夏彦のデビュー時と同様の衝撃を多くの読者と実作者に与えた。作品そのものは孤島の研究所を舞台とした、一種の「多重密室」ミステリである。14歳のときに両親を惨殺したとされ、それ以後この研究所内に幽閉されている天才科学者、真賀田四季という女性がきわめて魅力的に描かれる。当時はまだ新鮮だったインターネットをはじめとするコンピュータ・テクノロジーについての言及もあり、この作品は「理系ミステリ」といった呼ばれ方もした。しかし、それだけであればあそこまでの大きな話題を呼ぶことはなかっただろう。
森博嗣の作品が衝撃だった理由としては、身も蓋もないほど徹底した登場人物のキャラクター化にあった。主人公にして「探偵役」の犀川創平が「国立N大学の助教授」であるという造形は作者自身のプロフィールを思わせるが、もちろんこれは「私小説」などではない。恩師の娘で自らの教え子でもある西之園萌絵という学生をヒロイン(兼ワトソン役)に据え、犀川と萌絵との恋愛モードといってよい関係が描かれるのだが、「萌絵」という彼女の名前からもわかるとおり、字面によってすでに極端なキャラクター化がされていることがわかる。
「読本」のリバイバルとしての側面
かつて謎解きゲーム的な要素のつよい「本格」ミステリに対して投げかけられた言葉として、「人間が描けていない」という批判があった。それに対して、絵空事的な謎解きにいっそう磨きをかけることで応えたのが、京大推理小説研究会出身の綾辻行人(昭和62年に『十角館の殺人』でデビュー)、法月綸太郎(平成元年に『雪密室』でデビュー)らが主導して昭和末期から平成にかけて隆盛した「新本格ミステリ」のブームだった。
「新本格」の段階で、すでに名探偵役(有栖川有栖の火村英生や、さらに遡れば笠井潔の矢吹駆、島田荘司の御手洗潔など)のキャラクター化はかなり進んでいた。しかし「新本格」にはまだ、青春小説風の「自意識」の問題がどこか残っていた。「新本格」の第二世代ともいうべき京極・森が与えた衝撃は、そもそも自意識を抱えた「人間を描く」という発想が存在せず、はじめからすべてがキャラクターとして造形されていたことにあった。
京極夏彦が一作ごとに作品を超長大化させることで読者の驚きを呼んだのに対し、森博嗣は刊行ペースの早さで読者の度肝を抜いた。
平成9年のうちに森は『冷たい密室と博士たち』『笑わない数学者』も発表、翌年には同じシリーズの続編3作を、さらに翌年には4作を発表し、わずか3年で計10作のシリーズを完結させている。こうした書き方が可能であったのも、森博嗣もまた京極夏彦と同様、劇画的とも言えるほど極端に強くキャラクターを打ち出すという方法論をとっていたからだろう。京極と森は平成という時代を通じて膨大な作品を生み続け、ベストセラー作家でありつづけた。平成14年に『クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い』でメフィスト賞を受賞してデビューし、いまなお絶大なる人気を維持している西尾維新が、京極や森の正統なる後継者であることはいうまでもない。
京極夏彦や森博嗣が企て、西尾維新が完成させた小説のイノベーションは、じつは文学の更新というよりも、近世以前の「読本」への先祖返りという側面が大きいように思う。日本の近代文学がそのスタートの時点で切り捨てた、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』を典型とするキャラクター主導のエンターテインメントを、彼らは現代にふさわしいかたちでリバイバルさせたのかもしれない。
『文庫版 姑獲鳥の夏』
著者:京極夏彦 講談社(講談社文庫)
この世には不思議なことなど何もないのだよ――古本屋にして陰陽師が憑物を落とし事件を解きほぐす人気シリーズ第1弾。
東京・雑司ヶ谷の医院に奇怪な噂が流れる。娘は20箇月も身籠ったままで、その夫は密室から失踪したという。
文士・関口や探偵・榎木津らの推理を超え噂は意外な結末へ。
『すべてがFになる』
著者:森博嗣 講談社(講談社文庫)
孤島のハイテク研究所で、少女時代から完全に隔離された生活を送る天才工学博士・真賀田四季。
彼女の部屋からウエディング・ドレスをまとい両手両足を切断された死体が現れた。偶然、島を訪れていたN大助教授・犀川創平と女子学生・西之園萌絵が、この不可思議な密室殺人に挑む。
*本記事は、2018年08月23日に「monokaki」に掲載された記事の再録です。