
大ヒット作品の秘伝のタレ? 「貴種流離譚」と「英雄神話構造」を学べる作品|隆慶一郎『吉原御免状』|monokaki編集部
こんにちは。「monokaki」編集部の碇本です。
新学期&新年度が始まって二週間、新しい環境になった人もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
今まで違う日常は希望と不安を共に連れてくると思いますが、執筆の時間を確保するのも難しくなっている人もいるかもしれません。
もし、無理だと思ったら思い切って執筆を休んでみるのも大事なことかもしれません。そして、書きたいという気持ちが昂ってきたら、またあなたの小説を書けばいいと思います。
大事なのはあなたがしっかり作品に向き合える時間と体力と集中力を持つことだと思います。
今回は隆慶一郎『吉原御免状』を取り上げます。
隆慶一郎氏はもともと脚本家として著名な人でした。『水戸黄門』『鬼平犯科帳』『大忠臣蔵』『ご存知遠山の金さん』などの時代劇の脚本を手掛けています。
小説家になったのはなんと還暦をすぎたあとの61歳になってからとかなり遅いものでした。そのデビュー作が今回取り上げる『吉原御免状』です。隆慶一郎氏は1989年に亡くなってしまったため、小説家としての作家活動期間はわずか5年という短いものでした。
なぜ、今回『吉原御免状』を取り上げるのかというと、この時代小説はエンタテインメント作品として、時代小説をまったく読んでいなくても楽しめるものであり、物語の王道である「貴種流離譚」と「英雄神話構造」を持つからです。
「貴種流離譚」と「英雄神話構造」とは、多くの人気作品に内包されている物語構造です。「貴種流離譚」は、例えば、主人公は高貴な身分の出身だが、とある理由で両親に捨てられている。「英雄神話構造」では、主人公は一度死ぬこと(本当に死んでしまったり、象徴的に死ぬ形であったり)であの世(彼岸、物語論では「鯨の胎内」と言われることがあります」)に行って、そこで新たな能力を得て、この世(此岸)に戻ってくる、などがあります。
身近な「貴種流離譚」と「英雄神話構造」の例では大ヒット作『鬼滅の刃』があります。漫画を読みながら、どちらの要素や構造が使われているか考えるのも創作の練習になるのではないでしょうか。
これ以降、作品ネタバレを含みます。ネタバレされたくない方はお気をつけください。
4月1日(木):日本堤 - 皇子暗殺
松永誠一郎が、浅草日本堤の上に立ったのは、明暦三年(一六五七)、旧暦八月十四日の夕刻である。
(中略)
誠一郎は、二十五の齢まで、肥後の山中で生きて来た。そこでは、けものたちは、互いに相手の領分を犯すことなく、穏やかに、誇り高く、暮らしている。無用な殺気も、とげとげしい視線も、感じたことがない。
(どうして先生は、こんな猥雑な町へ行けと、遺言を残されたのか)
誠一郎の師は、宮本武蔵政名である。誠一郎は、棄て子。ものごころつく頃から、肥後の山中で武蔵に育てられた。師であると同時に父であった。
物語はこんな風に始まります。肥後の山中で育った松永誠一郎は江戸の色街である吉原にやってきます。それも亡き師匠であり育ての親だった宮本武蔵からの言いつけであり、彼の出自を巡る旅への召喚でもありました。
棄て子だった誠一郎の親とは誰なのか? といきなり冒頭から読者は謎を突き付けられて、ワクワクしながらページがどんどんと進んでいきます。同時に初めて山を下りて街に、そして吉原にやってきた誠一郎には見るものすべてが新鮮であり、「花魁(おいらん)」という存在すら知りません。誠一郎を気に入った白髪の老人・幻斎と出会うことになります。
師匠である宮本武蔵がかつて吉原(江戸に移転する前の吉原)から島原のいくさへ出陣していったという話と、武蔵が「雲井」という花魁のもとによく通っていたことを幻斎から聞かされて誠一郎は知ります。
また、幻斎が誠一郎に吉原における常識やしきたりを丁寧に教えていってくれるので、ちょっとした「吉原あるある」のようなものを覚えるのにも役に立ちます。そして、女を知らない初心な誠一郎に幻斎は吉原にいる花魁たちの業の深さについて教えていきます。そして、酒を飲み酌み交わしていくことで、父のような武蔵を失った誠一郎にとって吉原の父的な存在となり、未来へと導く役割をしていきます。
『スター・ウォーズ』におけるルークが誠一郎、ヨーダが幻斎と言えるかもしれません。ちなみに『スター・ウォーズ』も「貴種流離譚」や「英雄神話構造」のパターンをなぞっています。詳しく知りたい人は神話学のジョーゼフ・キャンベルの著書『千の顔をもつ英雄』を読んでみてください。『スター・ウォーズ』の監督であるジョージ・ルーカスもこの本を参考にして、『スター・ウォーズ』を作ったことは有名な話です。
隆慶一郎氏が『千の顔をもつ英雄』を読んで参考にしたのかはわかりませんが、世界中の神話や物語に出てくる王道パターンなので、知らずとこの構造を使ったのかもしれません。
吉原に来てそうそう誠一郎はある武士たちと関わったことで、生まれて初めて人を斬って殺めてしまいます。その相手は柳生一門のものでしたが、実は誠一郎が生まれた時から柳生一門と因縁があったことも徐々に判明していきます。
そして、吉原という男にも女にも極楽にも地獄にもなる場所で過ごしていくことで、山にいた時には感じなかった哀感のようなものを感じ始めます。剣の腕は一流だが、人間としてはまだ世間知らずの誠一郎を通して、人間の業や喜怒哀楽を隆慶一郎は描こうとしたのではないでしょうか。
勝山が初めて揚屋に赴く時は(これを道中という)、五丁町の太夫・格子が、一目見んものと、仲の町の両側に居並んだが、勝山はその中を、おめず臆せず、見事に揚屋通いの八文字を踏んで通ってみせた。この時、勝山が踏んだのは、外八文字である。それまでの太夫の道中は内八文字だったが、勝山の姿があまりに堂々と見えたため、以後、あらゆる太夫が外八文字を踏んだ。それほどの女である。
「………?」
なにか、ひどく柔らかなものが、誠一郎の背に押しつけられた。勝山が同じ縁台に坐って、からだを凭せかけて来たのである。当惑してそっとはずそうとすると、低い、だが甘やかな声が囁いた。
「ひとをお斬りなんしたね」
疑問ではない。既知の事実をさらりと云ってのけたような平明さがある。
「夢ですよ」
噂の早さに驚きながら、誠一郎は応えた。くす。勝山の柔らかい身体がはずんだ。
「何人斬った夢を見なんした」
「五人」
引きこまれるように、誠一郎は答えている。
「お強うござんすねえ。あちきは、強い殿御が、いっち好き」
ひどく冷たい手が、誠一郎の手に重ねられた。
「冷たい手だなァ」
誠一郎という男は、心底、園ての冷たさに驚いている。
「情の深い女子ほど、手は冷いものでありんす」
誠一郎は、ぞくっと身を慄わせた。勝山の指が、誠一郎の手の甲を、かすかに掻きあげたのである。勝山は微笑っている。更に甲から手首にかけて、そろそろと掻きあげてくる。触れるとも触れないとも分からぬほどの、かすかな触感が、誠一郎の男の気を微妙にかきたてている。誠一郎は狼狽した。
「いけないわ」
澄んだ声がいった。救われたような思いで、誠一郎は、声の主を見た。黒髪を切りそろえ、抜けるように色の白い女の子が、縁台の近くに立っている。齢が九つであることを、誠一郎はしっている。それは西田屋の主、庄司甚之丞のひとり娘、おしゃぶだった。
長い引用ですが、花魁の勝山と不思議な少女のおしゃぶ。この二人の女性が誠一郎の運命に大きく関わることになっていきます。おしゃぶはちょっと巫女やシャーマンぽい能力を持っている存在であり、この引用のあとには勝山が誠一郎の害を成す存在だと告げます。また、幼い少女は誠一郎と将来は結ばれるという未来も見えていたりと重要なキャラであることがわかります。
柳生一門をまとめる柳生宗冬との面会に望む誠一郎。彼が巻き込まれた戦いにおいて、『神君御免状』という奇怪な言葉を聞いており、そのことについて宗冬に聞こうと思っていたのです。しかし、柳生家には兄の宗冬がまとめる「表」の柳生と、宗冬の弟である烈堂こと義仙が率いる裏柳生が存在していました。誠一郎と戦ったものたちはその裏柳生のものたちだったのです。
話し合いがもたれていたところに、幻斎が三浦屋四郎座衛門という吉原の者を柳生の屋敷によこして、宗冬にある文を届けさせます。
『とりいそぎおしらせ申上げ候。御邸内にいらせられる、松永誠一郎さま、かしこくも後水尾院の御かくし子に御座候。お疑いの節は松永さま御佩刀を御一見くだされたし。かの鬼切の太刀に相違ござなく候』
ぽつんとそれだけ書かれている。
後水尾院は、法皇となられた後水尾帝のことであり、鬼切の太刀は、二代将軍秀忠から朝廷に贈られた、源家重代の名刀である。
宗冬の手から、書状が落ちた。奇怪な言葉が、その口をついて出た。
「なんという因果か!」
松永誠一郎はなんと法皇のかくし子だったのです。そして、後水尾院のおつきのものたちは徳川家からは邪魔な存在となって、柳生一門によって皆殺しされていました。その時に宮本武蔵に彼らの手の届かないところで育ててほしいと、赤子だった誠一郎と鬼切の太刀をおつきのものたち託されていたことが判明します。このことは誠一郎にはすぐには伝えられませんが、柳生一門の党首である宗冬がその25年前のことを思い出す形で読者には誠一郎の正体がわかるという展開になっていきます。
4月5日(金): 首代 - 裏
「柳生谷に急使を。急ぎ義仙と会いたい」
「義仙と話し合うまで、若者の素姓はいえぬ。義仙に話したものかどうか……」
宗冬は迷っている。逆効果になりかねない。二十五年前の怨みが、義仙の殺意を更にかきたてるかもしれぬ。もともと怨み深いたちであり、宗冬はそこがたまらなく嫌いなのだ。だが、狭川たち裏柳生が、独自に誠一郎の素姓を摑んだ時のことを思えば、どうしてもここで強い釘を打っておかねばならぬ。裏柳生の暴発は確実に表柳生を滅ぼすだろう。今日の吉原者たちの『本気』は、その予告であり、示威だったに違いない……。
「義仙」がどうしてもわしの意に従わぬと申すなら……
「いけませぬ」
内匠の顔色が変わっている。
「殿と義仙さまでは……」
さすがに、あとは続けられない。宗冬はほろ苦く笑った。
「わしが負けるというのか」
初代石舟斎は別格として、父宗矩と兄十兵衛は剣の天才だった。その才分は宗冬よりも義仙にうけ継がれているとは、柳生一門の定説だったのである。
「だが、それはどうかな」
冷たい薄笑いが宗冬の口もとに浮かんだ。策士野取内匠にさえ、この笑いは解けなかった。この瞬間、宗冬は、自分でさえ思いもかけぬ一つの決意を、はっきりと固めたのである。
この宗冬の決意が物語を大きく動かす要因となります。この時点で読者には表柳生と裏柳生があり、その柳生一門によって誠一郎は両親やその身の回りの世話をしていた者たちが皆殺しされたことを知っています。そして、誠一郎の正体を表柳生の党首である宗冬は知ることになりました。
これから誠一郎の敵になるであろうとわかる裏柳生の党首であり、宗冬の弟の義仙の存在も出てきました。皆さんだったら今後の展開はどうしますか?
物語の王道パターンの構造を持っているこの作品では、皆さんが今まで読んできた作品と結び付けて考えることができる展開となっています。
宗冬の決意とはなにか? 誠一郎に柳生一門の剣術の技術を教えるということです。つまり、本来は敵であり、彼に恨まれて当然の柳生家のトップである宗冬がその技術を伝えることになります。それはなぜか? 彼の弟である義仙と裏柳生が誠一郎を殺すために動き出すのが身内である彼にはわかっているからです。そのために誠一郎に柳生の剣術を教えることで義仙と裏柳生と戦える状態にしようとします。
誠一郎は幻斎から「敵娼(あいかた)」が決まったと言われますが、武蔵と山奥に住んでいて女っ気のなかった彼にとっては自分の相手をする花魁と言われても、ウブというか女性慣れしていないせいもあって拒みます。しかし、「神君御免状」のことを知りたいのであれば、女を知らねばならぬと言われます。
「どうしてですか? おなごとその言葉と何の関係が……」
「御免状は吉原の秘事だ。生まれついての吉原者か、よほど深く吉原に馴染んだ者にしか、明かすことは許されないのだよ」
「でも……」
「おなごを知らずして吉原を知ったといえるかね。吉原は、おなごの都ではないか」
これが幻斎の理屈である。誠一郎は負けた。お委せしますといってしまった。
「わしも委された責任上、いろいろ考え、ひとの意見もきいた上できめたことだ。大三浦屋の高尾太夫。太夫の中の太夫だ。これほどの女は、日本全国どこにいってもいやしない。どんな大大名の奥方だろうと、お公卿さまの姫君だろうと、とてもとても……」
ちなみに高尾太夫というのは落語にも出てきたりする有名な太夫ですが、実はひとりではありません。大三浦屋抱えの花魁によって、代々襲名された名前です。誠一郎の相手となるのはのちに仙台藩主伊達綱宗に見受けされることとなる仙台高尾という女性でした。
誠一郎の高貴な出自ですから、超一流の仙台高尾を幻斎がセッティングしたのはわからなくもないのですが、しかし、幻斎はなぜここまで誠一郎と吉原の関係性を深めようとしているのか。ここまで読んでいると幻斎の過去や吉原の成り立ちと「神君御免状」がこの物語の重要なキーだと思えてきます。
そして、誠一郎の敵娼をすることになる仙台高尾にあの不思議な少女のおしゃぶが話かけるシーンがあります。
禿ぐらいの齢である。高尾はついそういう目で見てしまう。禿の教育はいっさい姉さん役の花魁の責任なのである。
(齢頃になれば、あたたかい感じのいい花魁になるだろう)
童顔が変るのを、高尾はよく知っている。だが……。
「ありがとう。でもあたしは花魁にはなれないの」
まばたきもせずに、高尾の顔をみつけていたおしゃぶが、不意に、にこりと笑うとそういった。高尾はぎくっと身を引いた。
(この子はひとの心を読む……)
(中略)
「誠さまを、よろしくお願いします」
その目がきらりと光った。涙である。高尾は衝撃を受けた。
(この子は松永さまを情人(いいひと)のように想っている!)
おしゃぶが、小さく首を横に振った。高尾は間違っていた。おしゃぶの涙は、誠一郎に向けられたものではない。ほかならぬ高尾自身の運命に向けられたものだった。おしゃぶの目は、屋形舟から大川に吊され、無残に斬り殺される二年後の高尾の姿を見ていたのである。吊し斬りにしたのは、ほかならぬ伊達綱宗であった。
(誠さまの関わる女子はみな非業に死ぬ)
おしゃぶには、それが堪らなく悲しかった。
おしゃぶのこの発言によって、読者はこれから展開されるはずの誠一郎と仙台太夫の関係性がうまくいったとしても、このように未来のことを知ってしまったため、二人の関係性がより深くなっていくと同時にどこか悲しみを感じてしまいます。また、仙台太夫だけではなく、冒頭から登場している勝山が死ぬこともここで予言されていると言えるでしょう。
このあと、勝山は裏柳生のくノ一であることが読者にはわかります。ここで勝山と誠一郎は敵対する関係ですが、勝山は誠一郎を男としてみており、仙台太夫に嫉妬をするようになっていきます。ここでも男女関係が発生し、裏柳生の者である勝山は自らの使命と自分の思いに引き裂かれていく悲劇の女性となっていきます。
宮本武蔵の弟子であり、凄腕の剣客である松永誠一郎は法皇の血を引く皇子であり、そして徳川家の指南役である柳生家の技術も伝授されていきます。彼の出自と裏柳生との因縁によって、もうそこには死闘しかないのだろうなと思えてきます。
4月7日(水):大和笠置山 - 柴垣節
裏柳生の党首である義仙が吉原にやってきて尾張屋の二階座敷で踊っている幻斎の姿を見かけます。そして、柳生一族における剣の天才だった兄の十兵衛についての回想が始まるのですが、その兄である十兵衛を倒した相手がその小躍りをしていた若き日の幻斎だったのです。
幻斎と誠一郎は殺気を感じて、日本堤に出てそこから西方寺に出向きます。そこの和尚から預けていた長短二振りの唐剣を幻斎は受け取り、日本語ではない言葉でひとを斬る許しを神に願います。
そして、追ってきた義仙は十兵衛が死んだ日の事を尋ねると、幻斎はとぼけるようにして茶化しますが、戦いが始まると裏柳生のものが一瞬のうちに九人死体になってしまいます。
誠一郎は剣術の腕はあり、柳生の剣術を宗冬に教わり始めているとしても幻斎が強すぎてチートです。吉原を形成している人たちは幻斎のような武術を持ったものたちによって作られた場所だったということが明かされます。しかし、なぜ吉原はそんな強力な戦闘集団を作らねばならかったのか、という新たな疑問が出てきます。
「新吉原をなんだと思っているのだ。まわりには、お歯黒どぶという濠をめぐらせ、濠の手前は、石垣こそないが、小店と黒板塀で塞いでいる。濠の外はすべて足をとられる吉原田圃だ。奇襲と引揚げに便利なように、黒坂塀には九ヶのはね橋がかかっている。大手門ともいうべき大門が只一つ廓内への出入り口だが、そこには四郎兵衛番所がでんと頑張っている。更に五十間道の両側の編笠茶屋の中宿、これは悉く出城の如きものだ。山谷堀の水路さえ、わざわざ中途までしか拡げず、大門のまえまで舟が来れないようにしてある。そして退き口の守りにはこの三ノ輪の寮がある……」
誠一郎は茫然としている。いわれて見れば幻斎のいう通りである。
「では……新吉原は一箇の城ですか?!」
「当たり前だ。世間では、おはぐろどぶも、四郎兵衛番所も、花魁を逃がさぬための仕掛けと考えているが、あれはわしらがわざと弘めた噂なのだよ。だが見る者は見、知る者は知っている」
「でも……なんのための城ですか? 誰から誰を守るための……」
「無論、公儀から吉原を守るための城だ」
幻斎は、きっぱりといってのけた。
「公儀? ご公儀が吉原者を攻め滅ぼしたいわけが……」
「わけは大御所御免状にある」
幻斎の声が凄絶な気のために僅かに震えた。
この大御所御免状とは「神君御免状」のことです。御免状とは許可状のことであり、「神君」とは徳川家康のことなので、家康から何者かに与えられた許可状という意味になります。つまり、吉原を成立させている「神君御免状」とは徳川幕府の初代である家康が吉原という場所を作ってよいと許可を出したものだったのです。
幻斎の口からこの御免状は家康が死去の三日前に書いたものだということがわかるのですが、なぜもう亡くなるというときに家康はこの許可状を出したのか、それがこの物語の後半の大きな謎となっていきます。
そして、徳川幕府を家康の時代から支えた天海僧正という人物について幻斎は自分と同じように「死人」だと言い出します。幻斎は一度死んだことにして、違う人として生きていることを誠一郎に以前に伝えていたのですが、天海僧正の正体を明智光秀だとはっきり告げます。「本能寺の変」を起こしてすぐに殺されてしまったはずの、天下の謀反人である明智光秀です。
天海=明智光秀説は昔からあったものですが、この小説の中でもそれが取り入れられています。松永誠一郎は法皇の子であり、天皇家の血を引く高貴な出自だったわけですが、その対となるものこそが徳川幕府を開いて天下人となった徳川家康として物語では描かれていくことになります。
つまり、この作品において徳川家康は本物ではないという予感をこの時点で読者にさせているんですね。小出しに情報を出していくことで惹きつけていきます。
宗冬に剣術を教わる中で、誠一郎は自分の出自をとうとう知ることになります。その後、誠一郎と仙台太夫が「馴染」になる日が訪れます。「馴染」というのは夫婦になるということで、初めて寝所を客と太夫が共にすることになることをいいます。つまり、誠一郎はこれで男になります。昔の作品ですし、江戸時代を舞台にしているので、男が一人前になるというある種の「通過儀礼」として「初体験」が書かれています。
ここでも「貴種流離譚」と「英雄神話構造」という王道パターンが活きています。一度異界に行って帰ってくることで主人公が成長する。剣術の凄腕であっても世間知らずの誠一郎が「吉原」という異界(あの世のメタファ)でいろんなことを体験することで大人(人間として成長)になっていくわけですね。だから、シンプルな展開と言えばシンプルです。しかし、ここからはもう一人の主人公ともいえる徳川家康の物語も展開してくるという二重構造になっていきます。実はここからがめちゃくちゃおもしろいんです。
4月10日(土):八百比丘尼 - 歳の市
『吉原御免状』は宮本武蔵に育てられた松永誠一郎という天涯孤独の青年を主人公にした物語です。彼の出自がわかることが中盤までの大きな謎でした。彼が吉原にやってきてすぐに耳にした『神君御免状』という謎も同時に展開していました。そこから吉原がいかにできたのか、吉原者とは何者かという謎が明かされていきます。そして、『神君御免状』を出した徳川家康に影武者がいたという謎が後半には出てきます。
「monokaki」で以前に取り上げた「三幕八場構成」でも「出来事がエスカレートしていかないと、長編にならない」という話がありました。また、最初は「低い障害」があり、物語が進むとその障害がどんどん大きくなると物語はより面白くなるということも「三幕八場構成」を解説してくださった作家・脚本家の堺三保さんがおっしゃられていました。
この作品は「障害」というよりは「謎」がどんどん大きくなっていくことで、読者に先を読ませる求心力を持っているものだと思います。
甚内(ある事件で若き幻斎は「庄司甚左衛門」と新しい名前を名乗り始めます)は再び鷹狩りにやってきていた家康に吉原の許可を得るために殺される覚悟で出向きます。家康の護衛には裏柳生のものがいましたが、簡単に倒してしまい、家康に直訴します。そこには天海僧正も同席していたのです。
ここで家康と天海僧正の正体もはっきりと明かされます。彼らの正体を甚内が知ることで新「吉原」が建設された理由なども判明していきます。
「吉原」という場所がどうして作られたのか、なぜ家康が許可を出し、裏柳生からずっと監視され狙われているのかというこの物語の大きな仕掛けであり謎が読者にもわかります。この想像力と歴史上の人物たちをうまく組み合わせて物語ってどんどん読者を惹きつけていく筆力は素晴らしいです。
こういう作品を読んだ時には、作品の力によってジャンルを飛び越えることができるのだとわかってうれしいです。
最後には誠一郎と裏柳生のラストバトルがあります。そして、自らの出自を認めてもらう必要がある誠一郎はひとりで京に向かうため、吉原を出ていきます。そうやって物語は「行って帰ってくる」の構造のように、「吉原」にやってきた始まりから円環するように「吉原」を出ていくことで終わっていきます。
魅力的なキャラクターと出自などの謎だけではなく、「吉原」という場所を丁寧に描いたことで、一見突飛に見える世界観がより身近にリアリティを感じさせてくれる作品でした。
江戸時代を舞台にしていますが、物語の筋としては王道パターンが軸にあり、あなたが書くならどんな時代や場所にするかと考えながら読むとあなたが書きたい物語を書くきっかけになるのではないでしょうか。
というわけで、「名作読書日記」でした。
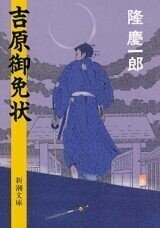
『吉原御免状』
著者:隆慶一郎 新潮社(新潮文庫)
宮本武蔵に育てられた青年剣士・松永誠一郎は、師の遺言に従い江戸・吉原に赴く。だが、その地に着くや否や、八方からの夥しい殺気が彼を取り囲んだ。吉原には裏柳生の忍びの群れが跳梁していたのだ。彼らの狙う「神君御免状」とは何か。武蔵はなぜ彼を、この色里へ送ったのか。――吉原成立の秘話、徳川家康影武者説をも織り込んで縦横無尽に展開する、大型剣豪作家初の長編小説。
「monokaki」は、エブリスタが運営する「物書きのためのメディア」です。
