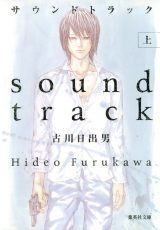「語り」と「ダンス」が小説に動きをもたらす|町田康と古川日出男|仲俣暁生
小説の世界に他のジャンルの表現者が参入することは、いまではもう珍しくもなんともない。音楽家や美術家、劇作家やマンガ家、さらにブロガーやAV女優や社会学者までが小説を書く時代である。しかしそうした「参入組」が、小説の世界にあらたな豊かさを持ち込めたかどうかは、厳しくジャッジしなければならない。
平成9年の第116回芥川賞は、エコーズというロックバンドでヴォーカリストをしていた辻仁成(平成元年に『ピアニシモ』でデビュー)の『海峡の光』と、劇作家の柳美里(平成6年に『石に泳ぐ魚』でデビュー)の『家族シネマ』が同時受賞したことで話題になった。このときの芥川賞には、INUというパンクバンドなどのヴォーカリストとしてカリスマ的な人気を得ていた「パンク歌手」、町田康の前年のデビュー作『くっすん大黒』も候補になっていた。
町田康は同作で小説家としてデビューする以前より、石井聰亙(現在は岳龍と改名)監督の『爆裂都市 BURST CITY』(昭和57年)、山本政志監督の『ロビンソンの庭』(昭和62年)といった映画作品にも出演しており、多彩な才能を各方面で開花させていた。
『くっすん大黒』は筒井康隆が審査員を務めた第7回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞し、以後、小説家としての活動が増えていく。平成12年には三度目の候補作『きれぎれ』で芥川賞を受賞。この一つ前の芥川賞では宮沢章夫の『サーチエンジン・システムクラッシュ』が候補になっており(結果は落選)、この時期の純文学シーンには異ジャンルからの参入が目立ったが、そのなかでも町田康の転身は見事だった。
平成版『大菩薩峠』ともいうべき傑作
初期は短編が中心であった町田康にとって転機となった作品は、平成16年に発表された長編『パンク侍、斬られて候』(マガジンハウス刊)だろう。
掛十之進という超人的な剣客を主人公とする、江戸時代が舞台のスラップスティックな「時代劇」だが、作品冒頭で巡礼の老人がほとんど意味なく惨殺される場面は、中里介山の超大作『大菩薩峠』をあきらかに意識している。掛十之進というアンチヒーローの造型も、もちろん『大菩薩峠』の剣客、机竜之助のパロディである。
掛十之進は、いま風に言えばフリーランスあるいは非正規雇用の牢人(浪人)だ。十之進は職を得るため、「腹ふり党」という新興宗教団体による危機が黒和藩に迫っている、というウソをでっちあげる。江戸時代の封建社会はいまのサラリーマン社会と同様、十之進のような根無し草を容易に受け入れない。だが黒和藩の重臣・内藤帯刀は政敵を追い落とすため、「腹ふり党」を利用しようとする。
このあたりのかけひきを描いた、内藤と十之進の会話は抱腹絶倒するしかない。
「そうなんだ。それでまあそういう直球主義で単刀直入に聞くけど、例えばまず、私がこうして自分の成功した軌跡、っていうか経緯について君に語っているのは掛くん、はっきりいってオヤジの説教入った自慢が始まった、と思っているのと違うかな?」
「そんなこと思ってません」
「よろしい。それでよろしいのだ。それで儂の直球主義をまともに訓戒として受け取って、はい、思ってます、なんていう馬鹿な小僧とは仕事ができんからな。では、もう一つ、ストレートに真顔で聞く」
「はい、なんでしょう」と訊ねる掛に内藤は、ねらねらした、甘えたような調子で問うた。
「君が腹ふり党を根絶できるというのは嘘なんだろ?」
掛は瞬間、絶句した。
内藤に雇われた十之進は「腹ふり党」がいまなお危険な存在であるかのような偽装工作を行うが、それは結果的に「腹ふり党」の復活をもたらしてしまう。最後はこの宗教団体と、人間の言葉を話すサル(大臼延珍)率いる猿軍団との壮絶な戦闘で物語は終わる。
「腹ふり党」の設定には、平成7年に東京都内の地下鉄で猛毒サリンを散布するなど一連のテロ事件を行った、オウム真理教のイメージも投影されているだろう。さらにいえば平成という時代を象徴するかのような閉塞感が、作品全体を覆っているように思える。
この物語の終盤で「大臼(でうす)」という、神の如き超越性を感じさせるサルを登場させた町田康は、その後の『告白』『宿屋めぐり』『ホサナ』といった「超長編」でも繰り返し、神や仏といった超越的な存在に言及するようになっていく。
音楽✕ダンス✕映画✕小説
平成10年、書き下ろしの長編小説『13』で幻冬舎からデビューした古川日出男は、文体の完成度でも物語性の豊かさでも新人離れしていた(正式のデビュー作『13』に先立ち、古川は『ウィザードリィ外伝II 砂の王(1)』というライトノベル作品を刊行した経験もある)。
矢継ぎ早に『沈黙』『アビシニアン』の長編2作を発表した後、平成13年に刊行した『アラビアの夜の種族』は翌年の日本推理作家協会賞と日本SF大賞を同時に受賞し、ミステリーとSFの両ジャンルで高い評価を受けた。
しかし古川はこうした「ジャンル小説」内での評価には飽き足らず、次々とスタイルの異なる作品を発表し、純文学とエンターテインメント小説との間の壁を確実に壊していった。平成18年に『LOVE』が三島由紀夫賞を受賞したことで、文芸誌での執筆機会も増えていく。古川日出男には町田康と同様に「超長編」も多く、その代表作である平成20年刊の『聖家族』は「メガノベル」とも呼ばれた。
多彩な作品を書き続けてきた古川日出男にとって、大きな転機となった作品を一つ挙げるとすれば、平成15年に刊行された『サウンドトラック』だろう。
それはこんな話だ。小笠原諸島・父島周辺で二人の小さな子どもが、それぞれの親に死なれて「孤児」になる。男の子の名前はトウタ。女の子の名前はヒツジコ。血縁のない二人はロビンソン・クルーソーにも等しい極限状況のなかを生き延びるが、やがて大人に発見されて身柄を保護され、兄妹として育てられる。
だがヒツジコとトウタはやがて引き離される。ヒツジコは本土の学校に通うようになり、トウタは島に残る。二人の再会はいつ、どのようにして起こるのか?
『サウンドトラック』はボーイ・ミーツ・ガールのこの物語を基本としつつも、両性具有のレニを第三の主要な登場人物として配し、ヒートアイランド化した東京に「レバノン」と呼ばれるアラブ世界を出現させるなど、きわめてカラフルでヘヴィな「近未来小説」だ(ちなみに「近未来」とは、私たちがすでに通りすぎた西暦2009(平成21)年である)。
この小説では音楽を拒絶するトウタと、超絶的な舞踊家となっていくヒツジコ、そして映像作家の役が割り振られてられたレニが対比的に描かれる。音楽やダンス、映画といった他ジャンルの「動き」を持ち込むことで、小説表現にさらなる強度を与えることが目論まれているのだ。
ヒツジコは揺らした。ヒツジコはわかっている。言葉ではわからないが、全身の細胞で正確無比に認識している。自分がダンスするのではない、自分はダンスすることによって他人の内面なかに眠っている感情を喚よび覚まして、その感情に当人を踊らせている、深層の欲求に相手をダンスさせていると。相手を、観察者を、あたしが揺れている姿を目撃した人間を。
朗読パフォーマンスや舞踊家・音楽家とのコラボレーションを熱心に行うようになってから、古川日出男が舞台演出家や戯曲家として豊かな経験をもつことが知られるようになった。この『サウンドトラック』という作品は、そのことをあらかじめ開示していたともいえるだろう。
古典作品の現代語訳がもたらしたもの
町田康と古川日出男の小説は、いっけん共通点が少ないように思える。「超長編」という点では同じでも、物語の進行を意識的に遅延させていく町田と、前のめりに突き進む古川とでは、その文体は対照的といってもいい。しかし、二人の小説には一つだけ共通点がある。それは「語り」(ナラティブ)に対する強い意識だ。
町田康の場合、代表作『告白』が「河内十人斬り」という河内音頭で語り継がれてきた事件を題材にしていることからもわかるように、音楽家としてのバックグラウンドだけでなく、落語や浪曲、音頭といった近世的な芸能のナラティブが身体化されている。古川日出男も自作の朗読パフォーマンスを何度も行っており、テキストを「声」として身体化することにきわめて意欲的な作家である。
「語り」に対する強い意識は、二人がともに古典作品の現代語訳やリメイクに取り組んだことでいっそう明らかになった。きっかけは平成26年から河出書房新社が刊行を開始した池澤夏樹・個人編集の「日本文学全集」である。
この全集で町田康は『日本霊異記 今昔物語 宇治拾遺物語 発心集』(平成27年9月刊)のうち宇治拾遺物語を、また古川日出男は『平家物語』(平成28年12月刊)をそれぞれ現代語訳している。
それぞれの訳文を少しずつ引用してみよう。まず町田訳『宇治拾遺物語』から。
お爺さんは心の底から思った。
踊りたい。
踊って踊って踊りまくりたい。そう。私はこれまでの生涯で一度も踊ったことがなかった。精神的にも肉体的にも。こんな瘤のある俺が踊るのを世間が許すわけがない、と思うまでもなく思っていて、自分のなかにある踊りを封印してきたのだ。けれども、もう自分に嘘をつくのは、自分の気持ちを誤魔化すのは嫌だ。私はずっと踊りたかったのだ。踊りたくて踊りたくてたまらなかったのだ。いまそれがやっとわかったんだ!
(「奇怪な鬼に瘤を除去される」)
次に古川訳『平家物語』からも有名な宇治川先陣の場面を。
佐々木が鐙を踏んばる。
佐々木が馬上に立ちあがる。
佐々木が、大音声で、名乗りをあげる!
「宇多天皇から九代の子孫、佐々木三郎秀義の四男、佐々木四郎高綱、宇治川の先陣なり! 我こそと思う人々あらば、来い。この高綱と組めや!」
佐々木は喚声をあげた。
進撃した、敵中に!
よ! た! は!
南無や、南無や、南無や!
三面の琵琶、絃の数ならば、あわせて十二!
撥三つ!
(「宇治川先陣――先駆けの名誉」)
「語る」ことの躍動に満ちたこうした古典作品とまみえたことが大きな刺激になったのか、町田康は義経記を大胆に翻案した『ギケイキ』の連載を開始(現在、第2巻まで刊行)。古川日出男は源氏物語を題材にした『女たち三百人の裏切りの書』についで平家物語の「異本」として『平家物語 犬王の巻』も刊行した。
町田康と古川日出男がいずれも古典作品から大きなインスパイアを得たのは、もともと二人の小説のなかに、近代文学のなかでは失われつつあったダイナミックな「語り」への身体感覚があったからだ。千年近い時を超えて、この二人の手により新旧の日本文学はたしかに「共振」したのである。
『パンク侍、斬られて候』
著者:町田康 角川書店(角川文庫)
強烈な言語パワーにあふれたシュールな世界!
町田康の真骨頂、ここにあり。
「腹ふり党」と称する、激しく腹を振って踊る新宗教が蔓延し、多くの藩が疲弊していた。
牢人・掛十之進はそのいかがわしい弁舌と剣の実力を駆使し活躍するが……。
『サウンドトラック』上巻
著者:古川日出男 集英社(集英社文庫)
近未来東京の少年・少女たち。衝撃の巨編!
2009年、東京崩壊。
2009年の東京はヒートアイランド現象が加速し、熱帯と化していた。
伝染病、異常気象、外国人弾圧運動…。
末期的な状況をサバイブする青年と女子高生たちの姿を描く新世代の青春小説。
*本記事は、2018年11月13日に「monokaki」に掲載された記事の再録です。