
自己破滅型の小説家が最後に書き終えた作品|太宰治『人間失格』|monokaki編集部
こんにちは。「monokaki」編集部の碇本です。
9月も後半に入り、今年も残り3ヶ月と少しになりました。来年の事を言えば鬼が笑うと言いますが、現状はまだ「コロナ」の猛威の終わりが見えないため、明るい未来を想像しにくい人の方が多いのではないでしょうか。
そう考えるとこの2年近くはそれ以前とは決定的に違う生活となり、ある意味では「非日常」だったものが徐々に「日常」になっていった時期であるとも言えます。
「非日常」を生きて、小説を書き続けた作家というと真っ先に太宰治のことが思い浮かびました。
今回は太宰治『人間失格』を取り上げます。
太宰治は第二次世界大戦前から戦後にかけて次々と作品を発表しました。それらの小説は現在に至るまでずっと読み継がれており、最後は女性と一緒に入水自殺した自己破滅型の小説家としても有名です。
太宰治が文学者として創作活動を行なったのは昭和八年の『思い出』から、昭和二十三年の『グッド・バイ』にいたる僅か十五年間である。しかもこの十五年間は、太平洋戦争を中心とする激動の時期、もっとも困難な悪しき時代であった。それにかかわらず、太宰治の文学は日本の文学として稀有の普遍性と国際性、そして今日も人々の魂に直接訴えかけてくるような不思議な魅力を持っている。
【本文166Pより】
上記は『人間失格』文庫本(新潮文庫)で奥野健男氏による解説の一部です。
書かれているように太宰治が作家として活動した期間とほぼ被るものが「十五年戦争」(1931年(昭和六年)の満州事変から日中戦争、そして太平洋戦争が終わる1945年(昭和二十年)まで全期間を一括する総称)と言われるものです。
太宰は「十五年戦争」が始まってから小説家となり、第二次世界大戦が終わるまでに代表作の多くを書いています。戦後から亡くなるまでにもいくつもの作品を発表していますが、彼にとっての戦後とはわずか3年しかなく、最後の完結作品となった『人間失格』は1948年に発表されています。
『人間失格』は総合雑誌『展望』で三回の連載でしたが、二回目が七月号に発表されたのは太宰が投身自殺を告げたと新聞やラジオが伝えた最中のことだったようです。現在の太宰治のイメージはどちらかというとこの戦後3年の作品と彼の行動が大きく影響を与えているとも言えるでしょう。
『文豪ストレイドッグス』『文豪とアルケミスト』という文豪たちをキャラクター化した作品でも「太宰治」はメインキャラクターの一人として人気があります。
文豪キャラクターとしても人気を誇る太宰治は『文豪ストレイドッグス』『文豪とアルケミスト』を通じて新しい世代が手に取る「文豪」であり、未だに若い読者を獲得している小説家でもあります。
今回は太宰治の最後の完結作品であり、未だに多くの人に読まれる代表作『人間失格』と「非日常」について考えてみたいと思います。
これ以降、作品ネタバレを含みます。ネタバレされたくない方はお気をつけください。
「はしがき」&「第一の手記」
私は、その男の写真を三葉、見たことがある。
【本文5P】
この作品の一番最初に書かれた文章が上記のものです。「はしがき」の最初にあり、小説家の「私」がこの物語の主人公である「大庭葉蔵」の幼年時代・学生時代、最も奇怪なとしの頃がわからない「三葉」(昔を思い出させる写真は詩的に「葉」で数えることがあります)の写真を見て、それぞれの感想について語ります。
「大庭葉蔵」は幼少期からお坊ちゃんとして裕福な家で育ち、顔立ちもほんとうにかわいらしいものだったようです。また、学生時代には美少年に育っていったのもわかります。しかし、としの頃がわからなくなっている時期のものは彼はひどく汚い部屋にいて、白髪も生えており、笑ってもおらず表情もないものでした。
この美しかった青年がなぜそんなことになってしまったのか?と読者に興味を感じさせる物語の導入部分となっています。そして、この「はしがき」と最後の「あとがき」は「私」によるもので第三者的な視線で書かれています。これ以降の「手記」は「大庭葉蔵」の一人称となっていきます。
恥の多い生涯を送って来ました。
【本文9Pより】
あまりにも有名な一文です。この文章から「第一の手記」は始まります。
東北の田舎に生まれた主人公である「大庭葉蔵」は十人ほどの家族の末っ子ですが、家が裕福だったため食うものに困るというようなことはなかったというのが回想の形で語られます。
この「大庭葉蔵」が語ることは著者である太宰治の人生を濃く反映したものであることから、自伝的な小説として読まれています。
何が欲しいと聞かれると、とたんに、何も欲しくなくなるのでした。どうでもいい、どうせ自分を楽しくさせてくれるものなんか無いんだという思いが、ちらと動くのです。と、同時に、人から与えられるものを、どんなに自分の好みに合わなくても、それを拒む事も出来ませんでした。イヤな事を、イヤと言えず、また、好きな事も、おずおずと盗むように、極めてにがく味い、そうして言い知れぬ恐怖感にもだえるのでした。つまり、自分には、二者選一の力さえ無かったのです。これが、後年に到り、いよいよ自分の所謂「恥の多い生涯」の、重大な原因ともなる性癖の一つだったように思われます。
【本文17Pより】
満ち足りているが故に、欲望のない子供だった葉蔵ですがこの時点でかなり冷めていて客観的に物事を見ていたようです。
また、家父長制の強い時代において絶対的な存在だった父に対しては、無邪気に甘えることもできず、本音を言うこともできなかったことが裏返しのように成長してからの自暴自棄な生活へ到った要因だったことがわかります。となると太宰治も同様のことがあったのでは、と思わせます。
けれども自分の本性は、そんなお茶目さんなどとは、凡そ対蹠的なものでした。その頃、既に自分は、女中や下男から、哀しい事を教えられ、犯されていました。幼少の者に対して、そのような事を行うのは、人間の行い得る犯罪の中で最も醜悪で下等で、残酷な犯罪だと、自分はいまでは思っています。しかし、自分は、忍びました。これでまた一つ、人間の特質を見たというような気持さえして、そうして、力無く笑っていました。もし自分に、本当の事を言う習慣がついていたなら、悪びれず、彼等の犯罪を父や母に訴える事が出来たのかも知れませんが、しかし、自分は、その父や母をも全部は理解する事が出来なかったのです。人間に訴える、自分は、その手段には少しも期待できませんでした。父に訴えても、母に訴えても、お巡りに訴えても、政府に訴えても、結局は世渡りに強い人の、世間に通りのいい言いぶんに言いまくられるだけの事では無いかしら。
必ず片手落のあるのが、わかり切っている、所詮、人間に訴えるのは無駄である、自分はやはり、本当の事は何も言わず、忍んで、そうしてお道化をつづけているより他、無い気持なのでした。
【本文22-23Pより】
葉蔵は幼少期に女中や下男から今でいう幼児虐待と性的暴行を受けていたことがわかります。その被害について父や母に言うこともなく、言っても無駄だと感じているその彼の性質が最終的に破滅へ向かっていく人生を予見させます。
この部分を読んで感じたのは「時代性」でした。『人間失格』は海外では少年への性的虐待を表現した小説であるともみなされています。しかし、日本では太宰治の代表作のひとつとして戦後から今に至るまでずっと読まれているにもかかわらず、女中にレイプされたという女性からの性的虐待やそれによる心的外傷が彼にどのくらいの影響を与えたかはさほど問題とならずに、葉蔵の破滅的な人生(≒太宰治の人生)への関心が向いているように感じます。
「monokaki」でも「時代性」について何度か取り上げているので、これから作家を目指す人はぜひ読んでみてください。下記の引用は「「ちょっと時代観の遅れた作家」にならないために」からです。「「時代性」って何ですか?」も参考になります。
時代の価値観の変容と共に名作の読み方や感じ方も変わっていくことは今後も起きていくと思います。
創作者も人間なので、もちろん学習によって変化・成長する機会は与えられて然るべきで、「過去」の発言をどこまで処罰の対象とするかはまだ議論の残るところですが、昨年から続く#MeToo 運動の盛り上がりなども含め、世界中で急速に新たな種類の「正しさ・公平さ」が整備されつつあるのは事実です。
そして日本国内の言説はそこから大きく遅れているということを、物書きならば認識しておいた方が良さそうです。わたしたちが普段何気なく口にしている自分の言葉、違和感なく受け取っている誰かの態度が、実はすでに「現代において問題のある言葉や態度」でも、無自覚にキャラクターの振る舞いに反映させている可能性があるからです。
「第一の手記」は16ページほどと短いものですが、「はしがき」で描かれた白髪になってとしの頃がわからなくなっている状態に葉蔵が堕ちていく原因の在処が書かれていました。この先を読むのは気が重くなります。
「第二の手記」
生まれてはじめて、謂わば他郷へ出たわけなのですが、自分には、その他郷のほうが、自分の生まれ故郷よりも、ずっと気楽な場所のように思われました。それは、自分のお道化もその頃にはいよいよぴったり身について来て、人をあざむくのに以前ほどの苦労を必要としなくなっていたからである、と解説してもいいでしょうが、しかし、それよりも、肉親と他人、故郷と他郷、そこには抜くべからざる演技の難易の差が、どのような天才にとっても、たとい神の子のイエスにとっても、存在しているものなのではないでしょうか。
【本文27Pより】
表面は相変らず哀しいお道化を演じて皆を笑わせていましたが、ふっと思わず重苦しい溜息が出て、何をしたってすべて竹一に木っ葉みじんに見破られていて、そうしてあれば、そのうちにきっと誰かれとなく、それを言いふらして歩くに違いないのだ、と考えると、額にじっとり油汗がわいて来て、狂人みたいに妙な眼つきで、あたりをキョロキョロむなしく見廻したりしました。できる事なら、朝、昼、晩、四六時中、竹一の傍から離れず彼が秘密を口走らないように監視していたい気持でした。
【本文29Pより】
幼少期から道化を演じ続けてきた葉蔵は中学校でその振る舞いを竹一という同級生に見破られてしまいます。そこからバカにしていたはずの竹一を手なずけようとします。この辺りが金持ちのボンボンの子供っぽいというか、人を上下関係において見下してしまっている感じがします。
自分は竹一にだけは、前から自分の傷み易い神経を平気で見せていましたし、こんどの自画像も安心して竹一に見せ、たいへんほめられ、さらに二枚三枚と、お化けの絵を画きつづけ、竹一からもう一つの、
「お前は、偉い絵描きになる」
という予言を得たのでした。
惚れらえるという予言と、偉い絵描きになるという予言と、この二つの予言を馬鹿の竹一に依って額に刻印せられて、やがて、自分は東京へ出て来ました。
【本文41Pより】
竹一とは友人関係になり、はじめて彼を自分の部屋にあげたときに、「お前は、きっと、女に惚れられるよ」と最初の予言をされています。そして、ここで書かれているのが第二の予言です。
物語の作中における「予言」というのは成就されるかどうかを読者に期待させて、ページを前に進めさせる要素にもなります。
酒、煙草、淫売婦、それは皆、人間恐怖を、たとい一時でも、まぎらす事の出来るずいぶんよい手段である事が、やがて自分にもわかって来ました。それらの手段を求めるためには、自分の持ち物全部を売却しても悔いない気持さえ、抱くようになりました。
【本文47Pより】
葉蔵が転落真っ逆さまなモードに突入し始めました。
「昭和」の時代までは「飲む・打つ・買う」というものは男のたしなみのような言われ方をしていました。
打つというのは博奕を打つということですが、金持ちの家に生まれた葉蔵は博奕はやらなかったようです。ただ、彼はこの先違う「打つ」をしていって完全に破滅していくことになります。
自分がまごついているので、女も立って、自分のがま口をのぞいて、
「あら、たったそれだけ?」
無心の声でしたが、これがまた、じんと骨身にこたえるほどに痛かったのです。はじめて自分が、恋したひとの声だけに、痛かったのです。それだけも、これだけもない、銅銭三枚は、どだいお金でありません。それは、自分が未だかつて味わった事の無い奇妙な屈辱でした。とても生きておられない屈辱でした。所詮その頃の自分は、まだお金持ちの坊ちゃんという種属から脱し切っていなかったのでしょう。その時、自分は、みずからすすんでも死のうと、実感として決意したのです。
【本文70Pより】
この女性のツネ子と葉蔵はこのあと入水します。そして、ツネ子だけが死んで、葉蔵だけが助かってしまいます。
実際に著者の太宰も21歳の時にバーの女給と入水自殺を図りますが、彼だけが生き残っており、そのことなどから今作が太宰の自伝的な私小説と言われる大きな要因となっています。
ただ、ここまで読んでも読者である私自身は、葉蔵のこれまでの人生やこの屈辱がトリガーとなって死のうと思った、という部分にはまったく共感できませんでした。
突然、れいの咳が出て来て、自分は袂からハンケチを出し、ふとその血を見て、この咳もまた何かの役に立つかも知れぬとあさましい駈引きの心を起し、ゴホン、ゴホンと二つばかり、おまけの贋の咳を大袈裟に附け加えて、ハンケチで口を覆ったまま検事の顔をちらと見た、間一髪、
「ほんとうかい?」
ものしずかな微笑でした。冷汗三斗、いいえ、いま思い出しても、きりきり舞いをしたくなります。中学時代に、あの馬鹿の竹一から、ワザ、ワザ、と言われて脊中を突かれ、地獄に蹴落とされた、その時の思い以上と言っても、決して過言では無い気持です。あれと、これと、二つ、自分の生涯に於ける演技の大失敗の記録です。
【本文76-77Pより】
葉蔵は入水自殺を失敗して助かった後に肺の疾患が見つかって入院します。その後、呼び出された検事の前で咳で出た血をハンカチにつけて、まるで大病を患わっているという演技をします。これがこの小説の名シーンの前フリとして機能することになります。
「小説や演劇で拳銃が出たら発射されなければならない」、そんな「チェーホフの銃」というテクニック(概念)があります。これは伏線の手法のひとつとして解釈されていますが、ストーリーには無用の要素を盛り込んではいけないという意味でもあります。つまり、ここで葉蔵が吐血するような演技をしてしまったのであれば、このあと彼は本当に吐血する状況になってしまうというわけです。
村上春樹さんの長編小説『海辺のカフカ』『1Q84』にもこの「チェーホフの銃」に関して登場人物が話しているシーンがあります。
「第三の手記」一
「自分でかせいで、そのお金で、お酒、いや、煙草を買いたい。絵だって僕は、堀木なんかより、ずっと上手なつもりなんだ」
このような時、自分の脳裡におのずから浮かびあがって来るものは、あの中学時代に画いた竹一の所謂「お化け」の、数枚の自画像でした。失われた傑作。それは、たびたびの引っ越しの間に、失われてしまっていたのですが、あれだけは、たしかに優れている絵だったような気がするのです。
【本文94Pより】
ここで葉蔵が言っている「失われた傑作」である自画像というのは美しい少年時代がすでに終わってしまったという意味に取れます。
また、竹一の予言のひとつだった「お前は、偉い絵描きになる」が外れた事も示唆しています。絵描きにはなれませんでしたが、漫画家として多少の収入を得るようになっていきます。
「しかし、お前の、女道楽もこのへんでよすんだね。これ以上は、世間が、ゆるさないからな」
世間とは、いったい、何の事でしょう。人間の複数でしょうか。どこに、その世間というものの実体があるのでしょう。けれども、何しろ、強く、きびしく、こわいもの、とばかり思ってこれまで生きて来たのですが、しかし、堀木にそう言われて、ふと、
「世間というのは、君じゃないか」
という言葉が、舌の先まで出かかって、堀木を怒らせるのがイヤで、ひっこめました。
【本文100Pより】
『人間失格』には何度も「世間」という言葉がでてきます。これが自己破滅的な太宰治が抗おうとしたもののひとつだったのかもしれません。しかし、人を道連れにして入水自殺しようとすんなよ、とは言いたくなります。
葉蔵は堀木という友人に「世間というのは、君じゃないか」という言葉が言えなかったのですが、ここでこの言葉をしっかりと口にしていれば、葉蔵は「人間失格」という状況にならずに済んだのではないかと思いました。ここがターニングポイントだったように、読後に感じました。
としが明けて厳寒の夜、自分は酔って煙草を買いに出て、その煙草屋の前のマンホールに落ちて、ヨシちゃん、たすけてくれえ、と叫び、ヨシちゃんに引き上げられ、右腕の傷の手当を、ヨシちゃんにしてもらい、その時ヨシちゃんは、しみじみ、
「飲みすぎますわよ」
と笑わずに言いました。
自分は死ぬのは平気なんだけど、怪我をして出血してそうして不具者などになるのは、まっぴらごめんのほうですので、ヨシちゃんに腕の傷の手当をしてもらいながら、酒も、もういい加減によそうかしら、と思ったのです。
「やめる。あしたから、一滴も飲まない」
「ほんとう?」
「きっと、やめる。やめたら、ヨシちゃん、僕のお嫁になってくれるかい?」
しかし、お嫁の件は冗談でした。
「モチよ」
(中略)
そうして自分たちは、やがて結婚して、それに依って得た歓楽(よろこび)は、必ずしも大きくはありませんでしたが、その後に来た悲哀(かなしみ)は、凄惨と言っても足りないくらい、実に想像を絶して、大きくやってきました。自分にとって、「世の中」は、やはり底知れず、おそろしいところでした。
【本文114-116Pより】
ほぼアル中な状態の葉蔵ですが、こんな嘘から出たまことが実現して結婚してしまいます。好きとか嫌いというよりも寂しいから、女性と一緒にいたいというのは彼が母性を無意識に求めていたからなのかもしれません。それに加えて美形だったので女性も寄ってくるという悪循環が発生しています。
幼少期の大庭家では彼の母親はほぼ出てきません。そして、女中などに弄ばれていたということを考えると、彼が女性と共に入水自殺を試みるのは母性を求めながらも、同時に復讐をしようとしていたのではと思えなくもないのです。実際のところどうだったのでしょうか?
「第三の手記」二&あとがき
「生意気言うな。おれはまだお前のように、縄目の恥辱など受けた事が無えんだ」
ぎょっとしました。堀木は内心、自分を、真人間あつかいにしていなかったのだ、自分をただ、死にぞこないの、恥知らずの、阿呆のばけものの、謂わば「生ける屍」としか解してくれず、そうして、彼の快楽のために、自分を利用できるところだけは利用する、それっきりの「交友」だったのだ、と思ったら、さすがにいい気持ちはしませんでしたが、しかしまた、堀木が自分をそのように見ているのも、もっともな話で、自分は昔から、人間の資格の無いみたいな子供だったのだ、やっぱり堀木にさえ軽蔑せられて至当なのかも知れない、と考え直し、
「罪、罪のアントニムは、何だろう。これは、むずかしいぞ」
と何気無さそうな表情を装って、言うのでした。
「法律さ」
堀木が平然とそう答えましたので、自分は堀木の顔を見直しました。
【本文123-124Pより】
葉蔵の友人としては最初はバカにしていた中学時代の竹一と、この画塾で知り合った6歳ほど年上の堀木が登場するのみです。この堀木は葉蔵に酒や煙草や女や左翼運動などを教える存在であり、影響力のある人物でした。しかし、葉蔵のように堕落していくこともなく、ほどほどにそれらを楽しみながら生きており、葉蔵とは対のような存在です。
人に本当の事は何も言わずに道化を演じていくことで孤独を感じ続けていた葉蔵にとっては、飄々としている堀木は「世間」を具現化したような人物だったのかもしれません。
東京に大雪の降った夜でした。自分は酔って銀座裏を、ここはお国を何百里、ここはお国を何百里、と小声で繰り返し繰り返し呟くように歌いながら、なおも降りつもる雪を靴先で蹴散らして歩いて、突然、吐きました。それは自分の最初の喀血でした。雪の上に、大きい日の丸の旗が出来ました。自分は、しばらくしゃがんで、それから、よごれていない個所の雪を両手で掬い取って、顔を洗いながら泣きました。
【本文137Pより】
「第二の手記」の最後にあった演技がここに本当のこととなりました。白い雪に真っ赤な血という印象的なシーンです。
蜷川実花監督&小栗旬主演映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』でもこのシーンが非常に印象的に撮影されていて、これがやりたくてこの映画を撮ったのではないかと思えるほどでした。
これは完全な死亡フラグの発動ですね。物語の終わりが近づいてきています。
モルヒネの注射液でした。
酒よりは、害にならぬと奥さんも言い、自分もそれを信じて、また一つには、酒の酔いもさすがに不潔に感ぜられて来た矢先でもあったし、久し振りにアルコールというサタンからのがれる事の出来る喜びもあり、何の躊躇も無く、自分は自分の腕に、そのモルヒネを注射しました。不安も、焦燥も、はにかみも、綺麗に除去せられ、自分は甚だ陽気な能弁化になるのでした。そうして、その注射をすると自分は、からだの衰弱も忘れて、漫画の仕事に精が出て、自分が画きながら噴き出してしまうほど珍妙な趣向が生まれるのでした。
【本文140Pより】
この「モルヒネ」を始めるきっかけはアル中状態から逃げる術だったのですが、より悲惨なことに滑り落ちていっています。博奕は打たなかった葉蔵が注射針を打つことで破滅の道から逃れることはもはや不可避になってしまいました。
「モルヒネ」は薬屋の奥さんがお店で渡してくれたことがきっかけでハマっていくのですが、ここまで来ると美貌の青年の葉蔵の美しさを周りが破壊しようと企んでいるようにも思えてきます。
神に問う。無抵抗は罪なりや?
堀木のあの不思議な美しい微笑に自分は泣き、判断も抵抗も忘れて自動車に乗り、そうしてここに連れて来られて、狂人という事になりました。いまに、ここから出ても、自分はやっぱり狂人、いや、廃人という刻印を額に打たれる事でしょう。
人間、失格。
もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました。
【本文147Pより】
「モルヒネ」を打ちつづけ廃人となった葉蔵は精神病棟に隔離されることになります。そこは患者も看護人も男ばかりで、彼の人生においては初めて女性がいない場所となりました。それが救いだったのかどうかはわかりません。ただ、ここは彼が抗おうとした「世間」すらない場所でした。
父が死んだ事を知ってから、自分はいよいよ腑抜けたようになりました。父が、もういない、自分の胸中から一刻も離れなかったあの懐しくおそろしい存在が、もういない、自分の苦悩の壺がからっぽになったような気がしました。自分の苦悩の壺がやけに重かったのも、あの父のせいだったのではなかろうかとさえ思われました。まるで、張合いが抜けました。苦悩する能力さえ失いました。
【本文148Pより】
葉蔵が入院してから三ヶ月ほど経ち長兄から父が胃潰瘍で亡くなったことを知らされます。彼の生き辛さの原因は父親だったのだと彼は悟ります。このあとに彼は退院して実家の援助を受けて東北の温泉地のはずれの古い家に住むことになるのですが、その時はまだ27歳でしかないのに白髪が増えてしまって40歳以上に見られるほどに老けてしまった、という場面でこの「手記」は終わります。
アル中になるのもヤク中になるのも身体が健康な人です。身体が弱い人は中毒になる前に決定的なことが起きてしまってその状態にはなりにくいので、葉蔵がもう少し体が弱かったらこんなことにはならなかったのではと思いました。
そして、彼がどこかで父親と向き合おうしたり、会いに行ったりして感情を爆発させたりしていたら、まったく違う結末になっていたはずです。
ここからの引用は冒頭の「はしがき」に出てきた「私」による「あとがき」になります。
この手記には、どうやら、昭和五、六、七年、あの頃の東京の風景がおもに写されているように思われるが、私が、その京橋のスタンド・バアに、友人に連れられて二、三度、立ち寄り、ハイボールなど飲んだのは、れいの日本の「軍部」がそろそろ露骨にあばれはじめた昭和十年前後の事であったから、この手記を書いた男には、おめにかかる事が出来なかったわけである。
【本文151Pより】
「昭和十年」(1935年)というと著者の太宰治が「太宰治」と名乗りだして小説を書き始めてから二年ほど経った頃です。同年には第一回の芥川賞の候補となって落選していたりもしますが、同時に鎮静剤のパビナールの依存症となっていきます。
ちょうど「満州事変」と「日中戦争」の間の時期であり、徐々に戦争に向かっていくという「非日常」に生活が変わっていく頃が作品の舞台だったということがわかります。
そして、戦後になってからあえてこの時期を最後の完結した小説として書き上げたのは、太宰治にとっても小説家としての人生を歩みだしたこと、そして戦時下に突入していくというそれまでの「日常」とは違う「非日常」に踏み出したと本人が強く認識していたからではないでしょうか。そして、その「非日常」が第二次世界大戦の終結と共に終わってしまって、元の「日常」がやってくると著者の太宰は死を選ぶことになったとも言えます。
「このノートは、しばらく貸していただけませんか」
「ええ、どうぞ」
「このひとは、まだ生きているのですか?」
「さあ、それが、さっぱりわからないんです。十年ほど前に、京橋のお店あてに、そのノートと写真の小包が送られて来て、差し出し人は葉ちゃんにきまっているのですが、その小包には、葉ちゃんの住所も、名前さえも書いていなかったんです。空襲の時、ほかのものにまぎれて、これも不思議にたすかって、私はこないだはじめて、全部読んでみて、……」
「泣きましたか?」
「いいえ、泣くというより、……だめね、人間も、ああなっては、もう駄目ね」
「それから十年、とすると、もう亡くなっているかも知れないね。これは、あなたへのお礼のつもりで送ってよこしたのでしょう。多少、誇張して書いているようなところもあるけど、しかし、あなたも、相当ひどい被害をこうむったようですね。もし、これが全部事実だったら、そうして僕がこのひとの友人だったら、やっぱり脳病院に連れていきたくなったかも知れない」
「あのひとのお父さんが悪いのですよ」
【本文154-155Pより】
「私」と会話しているのは「京橋のスタンド・バア」にかつていたマダムの女性です。大庭葉蔵が書いた「手記」を小説の材料になるかもしれないと三様の写真と三冊のノートブックを渡してくれたということになっています。しかし、マダムの「あのひとのお父さんが悪いのですよ」というセリフは葉蔵というか太宰の思いのように聞こえてきます。
「私」は小説家なので、やはり太宰治として考えていいのでしょう。そして、「手記」を書いた大庭葉蔵は「太宰治」と名乗っていた本名の津島修治だったように感じられる構成になっています。この『人間失格』は『展望』に三回掲載されたものですが、最後の第三回が掲載される前に太宰治が山崎富栄と共に入水自殺をして死んでしまったため、遺書のように現在まで読まれてきました。その事実を知らずに読むということがどうしても難しいので仕方ないとも思います。
当時、リアルタイムでこの連載を読んでいた読者にはほんとうに衝撃的だったと思います。今でいえばYouTuberが「YouTube」でリアルタイムでなにかをやらかしたのを見るに近い状態なのかもしれません。
太宰治という小説家は「非日常」の時代を生きて後世に残る小説をいくつも書き残しました。そして、「日常」に戻った世界で最後の完結した小説では自分の分身である「大庭葉蔵」が死んでいるであろうと示唆し、小説家としての「私」は死んでいないのだと書き残したのではないでしょうか。
というわけで「いまさら読む名作読書日記」でした。
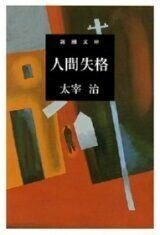
『人間失格』
著者:太宰治 新潮社(新潮社文庫)
「恥の多い生涯を送って来ました」。そんな身もふたもない告白から男の手記は始まる。男は自分を偽り、ひとを欺き、取り返しようのない過ちを犯し、「失格」の判定を自らにくだす。でも、男が不在になると、彼を懐かしんで、ある女性は語るのだ。「とても素直で、よく気がきいて(中略)神様みたいないい子でした」と。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う、太宰治、捨て身の問題作。
「monokaki」は、エブリスタが運営する「物書きのためのメディア」です。
